はじめに
在宅介護や介護現場で日常的に行われる「立ち上がり動作」。
一見シンプルに見えますが、実はこの動き、正しい方法を知らずに行うと、ご利用者様にも介助者にも大きな負担がかかることをご存じでしょうか?
たとえば、立ち上がりの際にバランスを崩して転倒してしまったり、介助する側が腰を痛めてしまったり…。
ちょっとした動作でも、身体の使い方を間違えると、大きな事故やけがにつながるリスクがあるのです。
しかし!立ち上がり動作の「コツ」や「正しい身体の使い方」を知るだけで、負担はぐっと軽減できます!
この記事では、理学療法士の視点から、立ち上がり動作に欠かせないボディメカニクスの基本と、スムーズに立ち上がるための具体的なポイントをわかりやすく解説していきます。
また、立ち上がり動作がズムーズに介助できれば、困っている方の多い移乗介助もグンと楽になりますので、是非とも最後まで読み進めてください。
高齢者の方の自立支援はもちろん、介助する皆さん自身の腰痛予防にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!
ボディメカニクスとは?〜立ち上がり動作の基本を理解する〜
ボディメカニクスとは、
体の動きや力の使い方を科学的に捉え、効率よく安全に動作するための原理のこと。
特に立ち上がり動作では、
- 支持基底面(身体が接地している面)
- 重心(体の中心にある重み) この2つを理解することが非常に重要です。
→重心は基本的におへそと思ってください。
座っている時の支持基底面は、お尻と太ももと足底。
立つときには、両方の足底。この支持基底面の真ん中に重心(おへそ)を移動させることが、スムーズな立ち上がりのコツになります!
詳しくはこちらの記事にまとめていますので、併せて読んでみてください。
▶︎介護技術を極める!ボディメカニクスの基本と実践
https://kaigoskills.com/body-machanics/
高齢者の立ち上がりが難しい理由
高齢者の場合、後方重心になりやすいのが特徴です。
これは、体が後ろに倒れそうな姿勢になっている状態。
理由は、
- 長時間座った生活習慣
- 筋力(特に足指の力)低下
- 恐怖心による前傾姿勢の不足 などが挙げられます。
結果、かかと側に体重がかかりすぎ、前への重心移動が難しくなってしまいます。
これが、立ち上がりにくさや転倒リスクを高めているのです。
立ち上がりをスムーズにするためのポイント
「お辞儀動作」で重心を前に移す
- おへそを膝に近づけるように「前傾」することで、自然と重心が足の間に移動します。
手引き介助でサポート
- 手を優しく前方に引くことで、無理なく重心を前に移動させます。
→手を引っ張って立たせると膝折れした時に対応できないので、肘を持って前腕を前方に引くようにしましょう。
自宅でできる立ち上がり練習方法
1. 丸椅子や歩行器を使う
前に手を置くことで重心が自然に前方に行き、立ち上がりやすくなります。
手すりを使用する場合は、前方に設置するようにしてください。
2. 足先の筋力トレーニング
足指を意識して踏ん張る練習も大切!足の指でタオルをたぐり寄せる練習(タオルギャザー)や、立位で手すりを持ったまま背伸びをする練習も効果的です。
支持基底面を広く保つ助けになります。
その方の転倒リスク等も考慮して実施してみてください。
3. 恐怖心を軽減する
安全な環境で、繰り返しゆっくりと練習を行うことで、自信を取り戻していきましょう。
車椅子からの移乗にも応用できる!
立ち上がり動作の基本を押さえておくと、車椅子からベッドや椅子への移乗動作にもスムーズに応用することができます。
移乗の際に特に大切なのは、「手を置く位置」と「重心移動」です。
ポイントは、ご利用者様の手をできるだけ体の前に置いてもらうことです。手すりを持つ際も、体の横にあるものではなく、前にあるものを持つようにしてください!
これにより、自然と前傾姿勢(お辞儀姿勢)が取れるため、重心を前に移動しやすくなります。
手を前に置くメリット
- 無理な力を使わず、スムーズに重心を前方へ移動できる
- 身体のバランスが安定し、ふらつきや転倒リスクを軽減できる
- ご利用者様自身が「自分で動けた」という自信を持ちやすくなる
重心移動をしっかりサポートできる!
介助が必要な方に対しては、さらに、介助者が前方より介助することで重心移動を自然に促しながら立ち上がりや移乗を手助けができます。
ご利用者様自身の筋力やバランス感覚を活かすことができるので、自立支援にもつながるのです。
介助者の腰への負担も軽減!
正しい重心移動ができると、ご利用者様の体重を無理に引き上げたり支えたりする必要がありません。
結果として、介助者の腰や背中への負担も大幅に軽減され、介護による慢性的な腰痛リスクを減らすことができます。
無理な力任せの介助は、お互いにとって危険を伴います。
立ち上がり・移乗動作の基本をしっかり理解し、安全で負担の少ない介護を目指しましょう!
ベッドの高さにも注意!
ベッドの高さは、立ち上がり動作のしやすさに大きく影響します。
特にベッドが低すぎると、重心を十分に前方へ移動できず、立ち上がる際に必要以上の筋力が求められます。
また、低い位置から体を持ち上げるためには、下から上へと重力に逆らう動作が必要となり、さらに大きな力が必要になります。
そのため、筋力が低下している高齢者にとっては、立ち上がり動作そのものが困難になる場合もあります。
適切なベッドの高さの目安
- 座面高40cm前後が一般的な目安ですが、ご利用者様の身長や脚の長さによって調整が必要です。
- 太ももがやや斜めになる角度(水平より少し膝が下がる程度)が、立ち上がりに理想的な姿勢です。
- 足裏がしっかり床につく高さであることが最も重要。足が浮いていたり、つま先だけしか接地していない状態では、踏ん張りが効かず安定した動作が難しくなります。
- 深く座りすぎないようにも注意してください。
高さを調整するだけで変わる!
介護用ベッド(特殊寝台)を利用されていない場合は、ベッドの脚に台を入れる、マットレスの厚さを変える、座布団を敷くなど、ちょっとした工夫で高さを調整することができます。わずかな違いでも、立ち上がりのしやすさや介助負担は大きく変化します。
イメージがつきにくい場合は、ご自身で体感してみることも大切なことです。
さらに重要!膝と足幅のポイント
立ち上がりをスムーズにするためには、膝の角度や足の幅(スタンス)にも注意が必要です。これらのポイントを押さえることで、安定した姿勢とバランスの良い重心移動が可能となり、介助負担の軽減にもつながります。

膝は「90度より少し曲がっている」状態が理想
- 座ったときに膝がやや深く曲がっていることで、重心を前に移動しやすくなります。
- ただし、ふくらはぎがベッドフレームに強く当たらないように、位置や角度には注意しましょう。接触があると、立ち上がり時に動作が妨げられたり、不快感を与えることがあります。
- ベッドの位置やご利用者様の着座位置を調整することがポイントです。
足幅は「肩幅程度」が基本
ご利用者様の姿勢を横から確認し、足がまっすぐ正面を向いているか、左右に傾いていないかもチェックするとより効果的です。
また、足の幅は狭すぎると不安定になり、広すぎると力が発揮できません。
肩幅程度に開くことで、バランスが取りやすく、安定した支持基底面を作ることができます。
まとめ
立ち上がり動作を「理解」することで、介護はもっと楽になる!
立ち上がり動作は、在宅介護や施設介護の現場で最も頻繁に行われる基本の動きのひとつです。
しかし、「ただ立つだけ」と侮ることなく、ボディメカニクスに基づいた正しい身体の使い方を知ることで、ご利用者様の自立支援はもちろん、介助者の腰痛予防にもつながります。
今回ご紹介したポイントはどれも、特別な道具や筋力を必要とせず、すぐに実践できる内容ばかりです。
- 重心移動の意識
- 足幅・膝の角度
- ベッドや椅子の高さの調整
- 安全な環境づくりと繰り返しの練習
こうした基本を押さえるだけで、立ち上がり動作はぐっと安定し、安全で楽な介助が可能になります。
そして、立ち上がりの工夫はそのまま移乗介助にも応用が可能。
ご利用者様の「できた!」という達成感にもつながり、自信と自立をサポートする第一歩となります。
ぜひ、明日からの介護に取り入れてみてください。
小さな工夫と知識の積み重ねが、安全で質の高い介護を支えていきます!
YouTubeでもこちらの内容は説明しています。
合わせてご視聴して理解を深めてくださいね。
▶︎YouTubeで見る
立ち上がりから学ぶ【ボディメカニクス】立ち上がりの基礎がわかると移乗が楽になる‼️
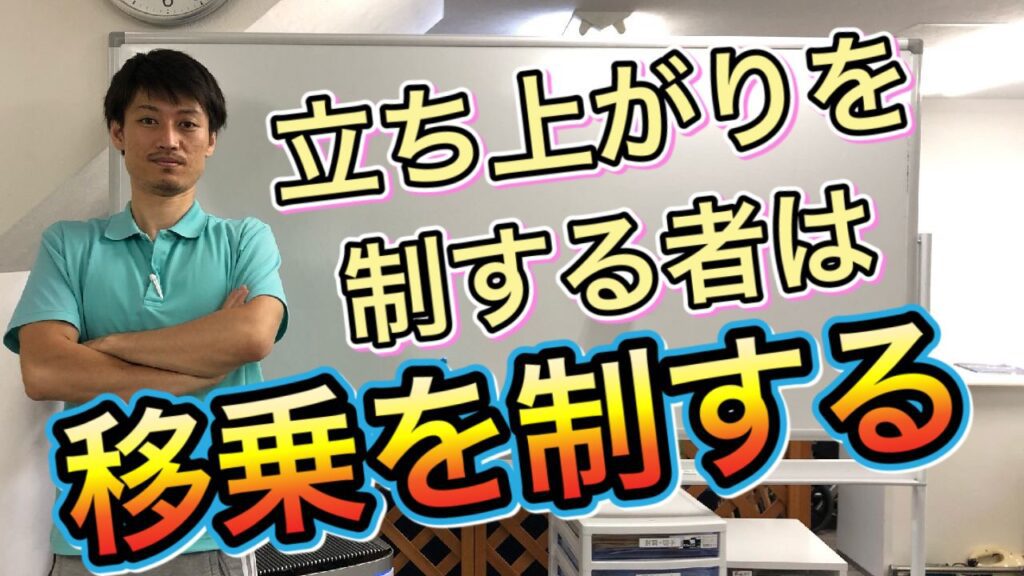

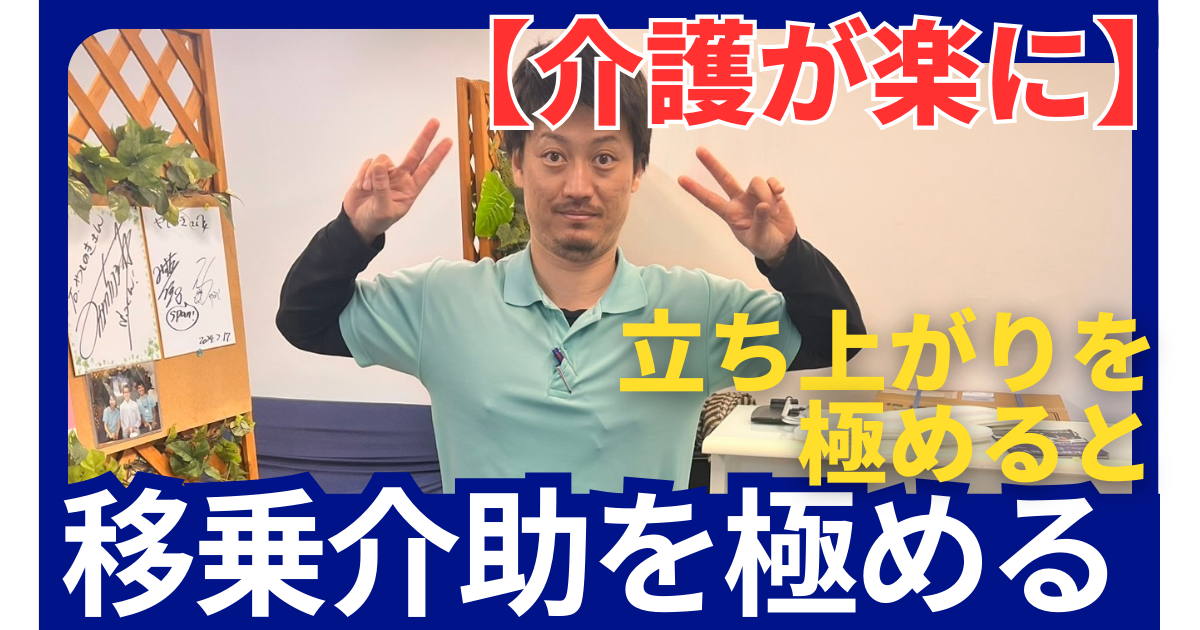
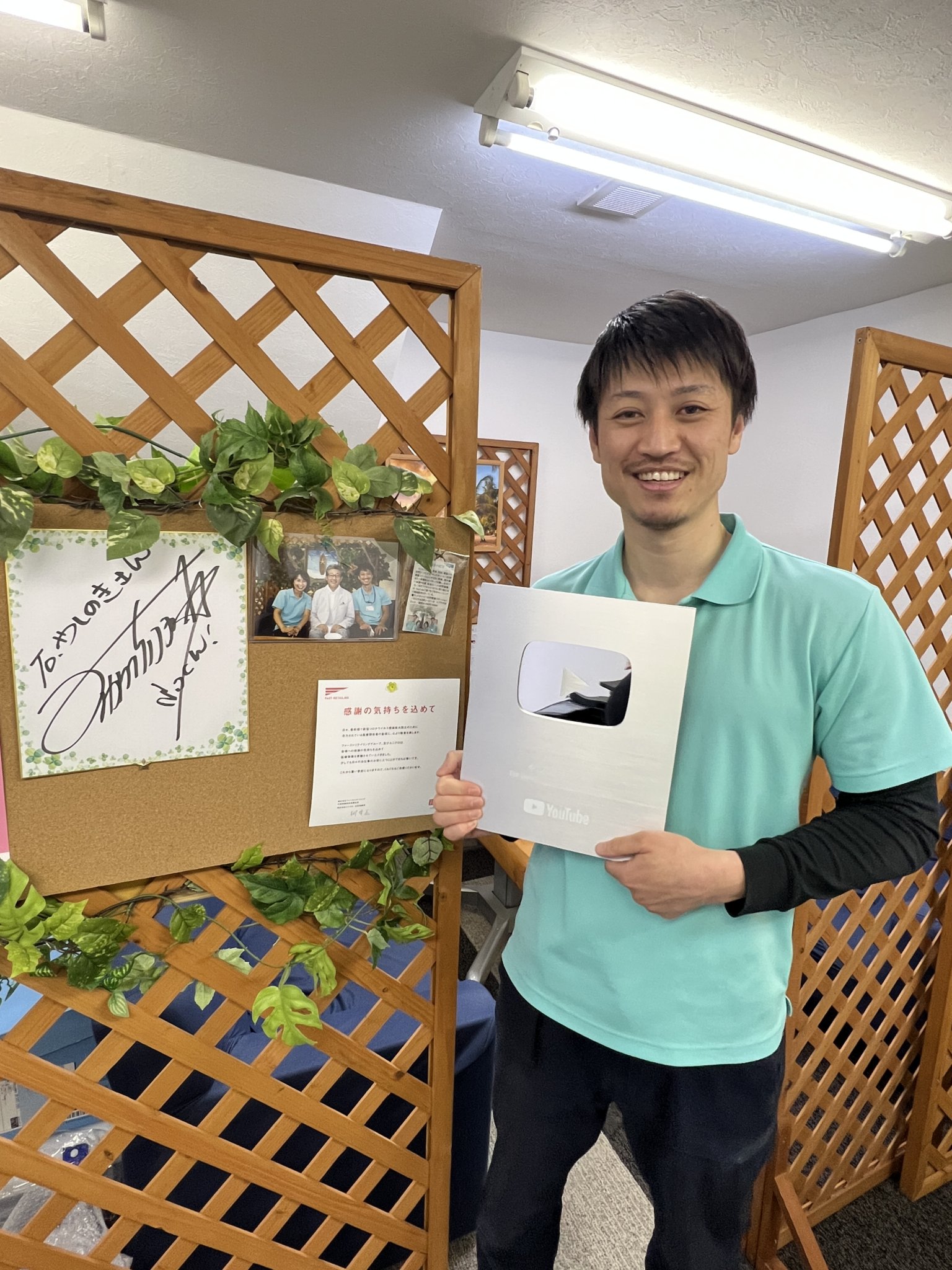
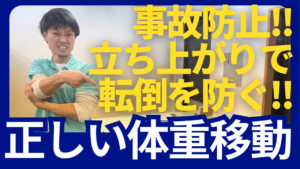
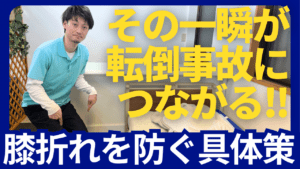
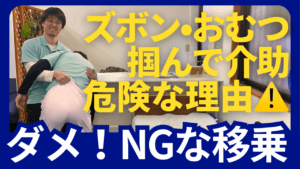
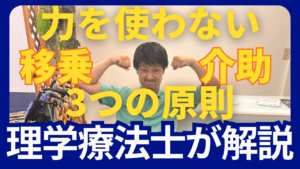
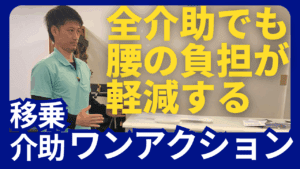
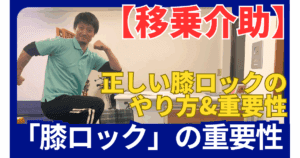
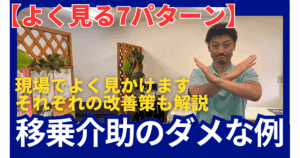
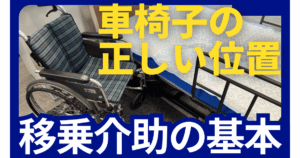
コメント