はじめに
介護や医療の現場では、日常的に多くの専門用語が使われます。これらの言葉を理解しておくことで、職員同士のコミュニケーションがスムーズになるだけでなく、専門用語ではない言葉に比べ、理解が早くなることもあります。
最近では、介護・医療スタッフの間でも、現場の記録などでできるだけ専門用語を使わず、他職種にも分かりやすく、ご利用者様やご家族様にも理解しやすい言葉で伝えることが求められています。
しかし、私自身も含め、専門職として長年働いていると、無意識のうちに専門用語を使ってしまったり、どこからが専門用語で、どこまで丁寧に話せばいいのか分からなくなることもあり、まだまだ現場では専門用語が飛び交っているのが現状です。
そこで今回は、介護や医療の現場でよく使われる言葉をできるだけ分かりやすく解説していきます。
介護の基本姿勢に関する用語
① 背臥位(はいがい)
背臥位とは、仰向けに寝た状態を指します。
リラックスできる基本の姿勢ですが、長時間同じ姿勢でいると「褥瘡(じょくそう)床ずれ」ができやすくなるため、定期的な体位変換が必要です。
② 仰臥位(ぎょうがい)
仰臥位は、背臥位と同じ意味で、医学用語として使われることが多い言葉です。
病院やリハビリの場面では「仰臥位」、介護の現場では「背臥位」という表現がよく使われるようです。
③ 側臥位(そくがい)
側臥位とは、横向きに寝た状態のことです。
背臥位よりも呼吸が楽になりやすく、褥瘡予防のための姿勢としてもよく使われます。特に、右側を下にする「右側臥位」、左側を下にする「左側臥位」と細かく区別されることもあります。
④ 伏臥位(ふくがい)
伏臥位とは、うつ伏せに寝た状態を指します。腹臥位とも呼ばれます。
呼吸器のリハビリなどで活用されることがあり、肺の機能改善や全身の筋肉を伸ばす効果があります。しかし、高齢者にとっては負担が大きいため、適切なサポートが必要です。
⑤ ファウラー位
ファウラー位とは、ベッドの背もたれを45度ほど起こした姿勢です。半臥位とも呼びます。
心臓や呼吸器系の疾患がある方にとって楽な姿勢とされています。
ベッドの背もたれを15~30度にした場合はセミファウラー位といいます。
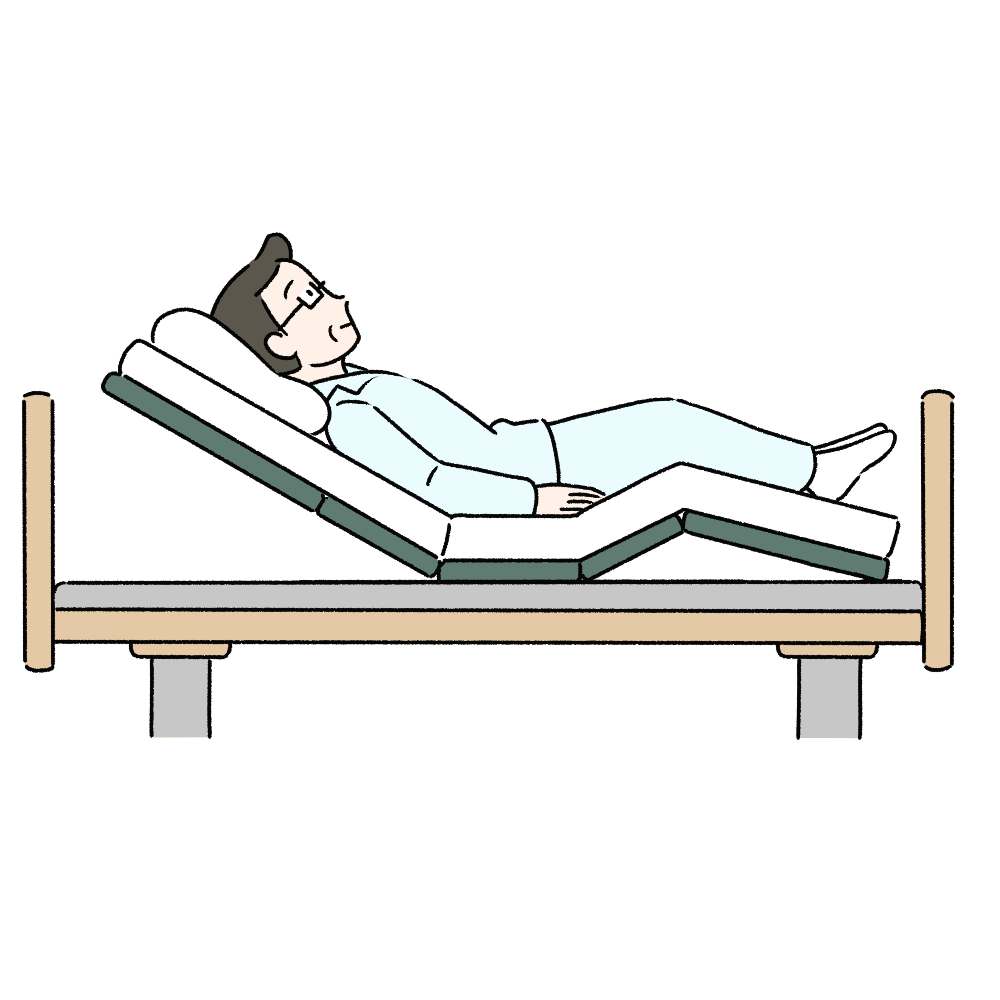
⑥ ギャッチアップ
ギャッチアップとは、特殊寝台(介護用ベッド)の背もたれや膝部分を調整して角度を変えることを指します。
座位をとる際や、食事・排泄の際に活用されます。
背もたれ部分のみを上げるときは、ヘッドアップということもあります。
介助・動作に関する用語
⑦ 移乗(いじょう)
移乗とは、ベッドから車椅子へ、逆に車椅子からベッドへ、椅子からトイレへ移るなど、座る場所を移動する動作のことです。介護技術で苦労されている方の多くは、この移乗で困っているのではないかと思います。
当ブログでも移乗介助は詳しく解説していきます。
⑧ 起居(ききょ)
起居とは、起き上がることと横になることの両方を指します。
ベッドや布団からの起き上がり、座位からベッドや布団に寝転がることです。
⑨ 端座位(たんざい)
端座位とは、 ベッドや椅子の端に座る姿勢のことです。
また座位にもさまざまあり、足を伸ばして座ることは長座位と呼び、テーブルや机に枕を乗せ、そこにもたれかかるように座ることを起座位と呼びます。
⑩ 離床(りしょう)
離床とは、ベッドから起き上がり、車椅子や椅子へ移ることを指します。
長時間寝たきりにならないよう、離床を促すことが重要です。
また、移乗の際にお尻が座面から離れることを臀部離床といいます。
⑪ 体位変換(たいいへんかん)
体位変換とは、ご利用者様の姿勢を定期的に変えることです。長時間同じ姿勢で寝ていることは、関節拘縮や褥瘡(床ずれ)のリスクを高めるため、褥瘡や関節拘縮を防ぐために重要なケアの一つです。
⑫ 移動介助(いどうかいじょ)
移動介助とは、ご利用者様の歩行や移動をサポートすることです。「移乗」も移動介助の一部です。
※介助・動作に関する用語の項に関しまして、これらの介助にはボディメカニクスは必須になってきます。
詳しくは当ブログ記事でも説明していますので、ぜひ一度読んでみてください。
▶︎介護技術を極める!ボディメカニクスの基本と実践
https://kaigoskills.com/body-machanics/
介護の介助レベルに関する用語
⑬ 全介助(ぜんかいじょ)
ご利用者様が自力で動作を行えず、ほぼ100%の介助が必要な状態を指します。
⑭ 一部介助(いちぶかいじょ)
ご利用者様が部分的に動作を行えるが、一部サポートが必要な状態です。
軽介助、中等度介助、重介助など介助レベルによって使い分けることもあります。
⑮見守り(監視)
介助は不要だが、見守りが必要な状態です。
いつでもすぐに支えられる距離で見守る場合は「近位見守り」、遠くから声かけのみサポートが必要な場合は「遠位見守り」といいます。
⑮ 自立(じりつ)
ご利用者様が日常生活動作をほぼ自力で行える状態を指します。
介護に関わる職種の用語
⑰ 理学療法士(PT:Physical Therapist)
理学療法士は、歩行訓練や筋力強化など、身体機能の回復を目的としたリハビリを担当する専門職です。
また、座位、立位、起居、移乗、歩行などの基本動作のリハビリを専門的に行うことが多いです。
当ブログ運営者も理学療法士の資格を持っています。
⑱ 作業療法士(OT:Occupational Therapist)
作業療法士は、手や指のリハビリ、日常生活動作の訓練を専門とする職種 です。
日常生活動作とは、トイレ動作や入浴動作、調理や着替えなどの日常生活で必要とする動作のことです。基本動作の対義語として、応用動作とも言われることがあります。
⑲ 言語聴覚士(ST:Speech Therapist)
言語聴覚士は、発声や嚥下(飲み込み)に関するリハビリを担当する専門職です。
⑳ 介護支援専門員(ケアマネージャー)
ご利用者様が適切な介護サービスを受けるためにケアプランを作成し、各サービスの調整を行う専門職 です。
例えば、A様に対して、福祉用具で車椅子と介護用のベッドのレンタルをし、訪問看護で週に一回看護師が体調確認と薬の確認等を行い、訪問看護のリハビリを週に2回利用するなどを調整、手配することです。
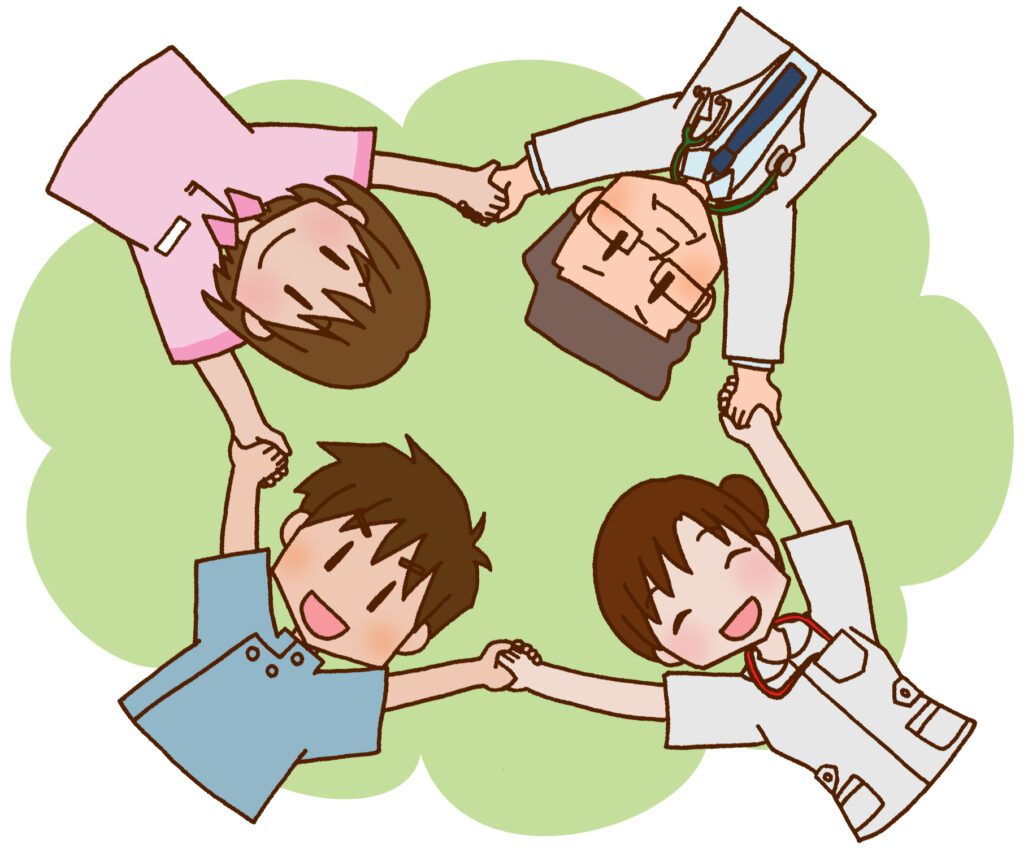
これらの専門職がチームになって1人のご利用者様を支援しています。
介護サービスに関する用語
㉑ ケアプラン
ご利用者様がどのような介護サービスを受けるかを決めるケアマネージャーが作成する計画書です。
㉒ ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)
日常生活で行う基本的な動作(食事、排泄、入浴、歩行など)を指します。
㉓ IADL(Instrumental Activities of Daily Living:手段的日常生活動作)
買い物、料理、洗濯、金銭管理など、より高度な日常生活動作を指します。
㉔ QOL(Quality of Life:生活の質)
ご利用者様が どれだけ満足のいく生活を送れているかを示す指標 です。
ご利用者様と介護者に関する用語
㉕ ご利用者様
当ブログでは、介護・介助を受ける方や、介護サービスを受ける方を「ご利用者様」と統一しています。
「利用者」「入居者」「患者」と呼ばれることもありますが、敬意を込めて「ご利用者様」と表記します。
㉖ 介護者・介助者
- 介護者:主にご家族様など、ご利用者様の日常的な介護を担う人を指します。
- 介助者:介護施設の職員やヘルパーなど、専門的な支援を提供する人を指します。
当ブログでは、介護者や介助者を、介護・介助する側の人をさして使っています。
㉗ 褥瘡(じょくそう)
褥瘡とは、 長時間同じ姿勢でいることで皮膚にできる「床ずれ」 のことです。
寝たきりの方に多く、定期的な体位変換やクッションの使用が予防に効果的です。
深刻な状態になる前に、予防や早期発見がかなり重要です。
㉘ 関節拘縮
関節拘縮とは、関節が硬くなり動かしにくくなる状態です。長期間の寝たきりや運動不足が主な原因で、放置すると悪化します。早めのケアが大切です。
まとめ
今回は、介護現場でよく使われる専門用語を詳しく解説しました。日々の介護や業務で役立てていただければと思います!介護の仕事をする上で役立つ知識なので、ぜひ覚えて活用してみてください!
YouTubeでも専門用語の解説をしています。今回の記事の内容とは異なる用語もありますので、ぜひみてみてください。
▶︎YouTubeの動画を視聴する
介護現場で知っておくべき用語①】知ってるだけでレベルアップ‼︎
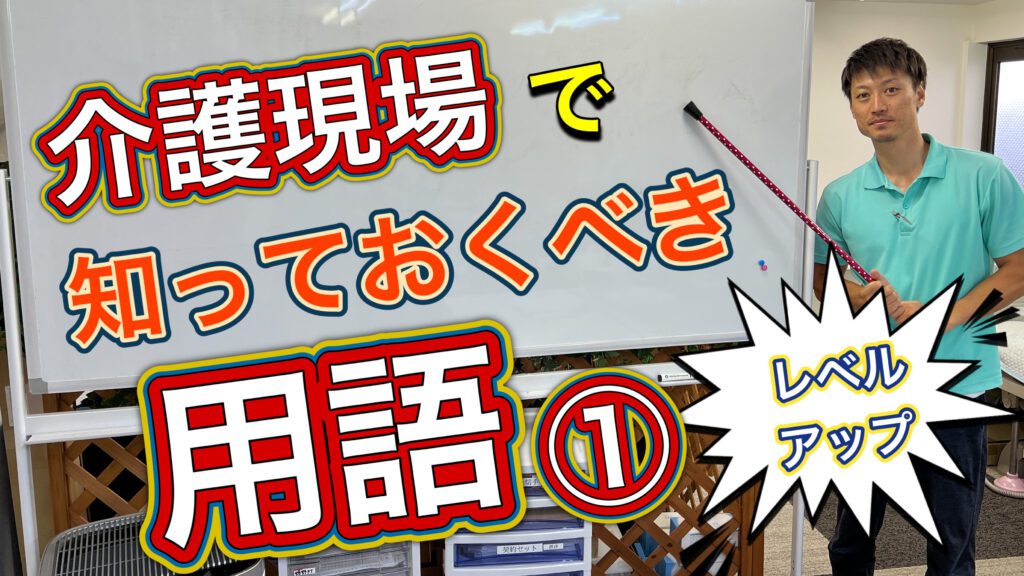

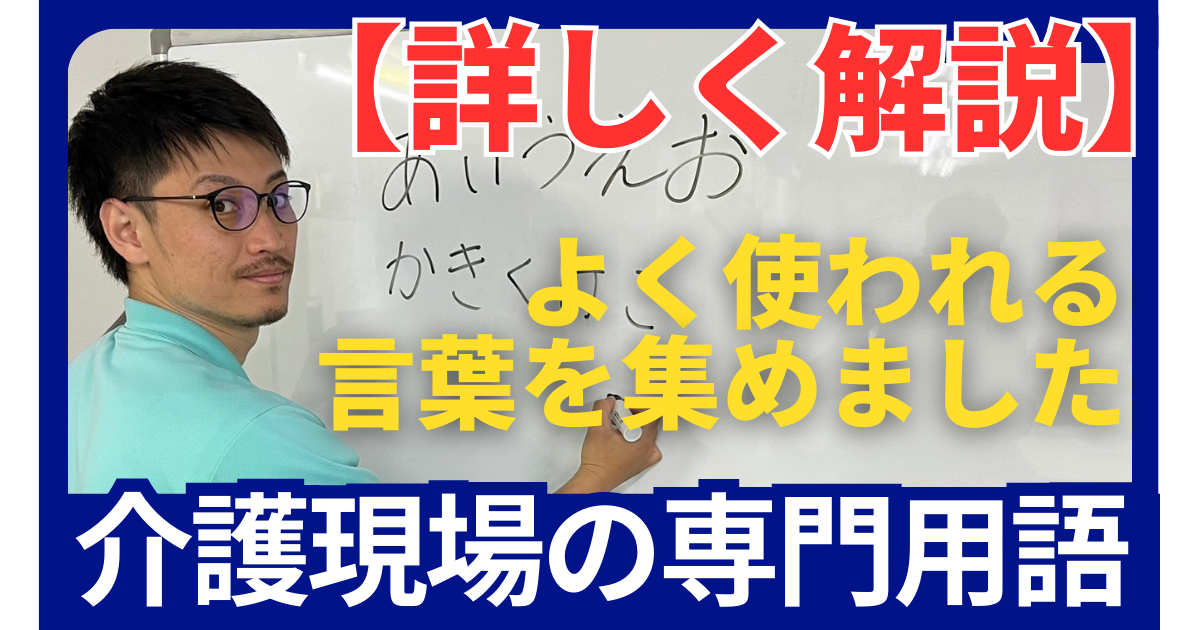

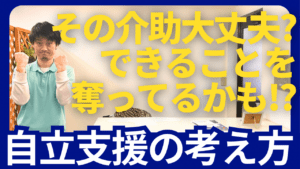
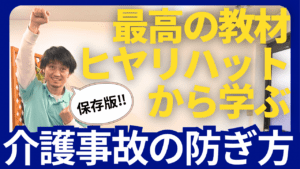
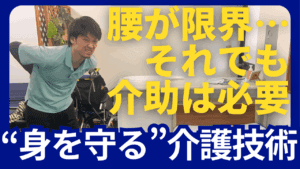
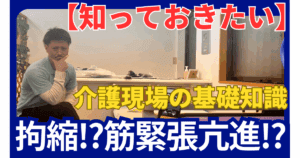
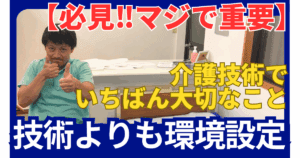
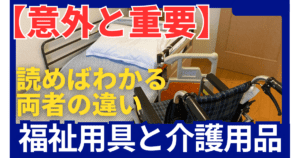
コメント