はじめに
パーキンソン病の方に対する歩行介助は、介護の中でも特に細やかな配慮と工夫が求められる場面です。
「足が前に出にくい」「小刻み歩行になる」「急に止まってしまう」「転びやすい」といった特徴があり、ただ手を取って支えるだけでは、ご利用者様にとって安全かつ快適な歩行は実現できません。
実際の介護現場では、
- 「どう声をかければ動きやすいのか?」
- 「どこに立って支えたら安心なのか?」
- 「万が一転倒しそうになったらどう対応するのか?」
といった悩みを抱える介助者も少なくありません。特にパーキンソン病の歩行は日によって症状の出方が変わるため、昨日できたことが今日は難しいというケースも多くあります。
また、ご利用者様ご本人にとっても「思うように体が動かない」ことは強い不安やストレスにつながります。歩行は移動手段であると同時に、自立や尊厳を支える大切な行為です。そのため、適切な介助ができるかどうかは、生活の質(QOL)にも直結します。
パーキンソン病の歩行の特徴
パーキンソン病の方に見られる歩行の特徴を知ることは、介助の第一歩です。
ただ「歩きにくい」と一言で片づけるのではなく、症状ごとの特徴を理解しておくことで、より安全で適切な介助につなげることができます。
すくみ足
歩き出そうとしたときや、狭い場所・方向転換の際に、まるで足が床に張りついたように出なくなる現象です。信号待ちからの歩き出しや、トイレの出入り口などでよく見られ、転倒リスクが高まります。
小刻み歩行
一歩一歩の歩幅が小さくなり、前傾姿勢のまま小さなステップを繰り返す歩き方です。スピードはそれほど出なくても、体が前に流れるため止まりづらくなります。日常生活では「気づいたら机にぶつかっていた」といったことも少なくありません。
突進現象
重心が前に傾いたまま止まれず、前方へ突き進んでしまう現象です。本人は止まりたいのに体が前に出てしまい、勢いのまま転倒する危険が非常に高い状態です。介助者にとっても目が離せない瞬間です。
姿勢反射障害
バランスを崩したときに体勢を立て直す反応が弱く、ちょっとした刺激で転倒してしまいます。健常な人であればとっさに足や手を出して支えられますが、パーキンソン病の方はその反応が乏しいため、倒れると大きなケガにつながりやすいのです。
すり足歩行
足の裏が床から離れにくく、靴や床の段差、カーペットの端などに引っかかりやすい歩き方です。見た目には大きな変化がないように思えても、転倒の大きなリスク要因となります。

歩行介助の基本的な考え方
パーキンソン病の歩行介助で大切なのは、「ただ支える」のではなく、ご利用者様の特徴に合わせた工夫をすることです。以下の5つのポイントを意識することで、転倒予防だけでなく、ご利用者様が安心して歩ける環境をつくることができます。
①ご利用者様のペースを尊重する
急かしたり、強引に動かそうとすると、すくみ足が強く出て余計に足が前に出にくくなります。
特に「早く歩いてください」「こっちに来てください」といった急かす言葉は逆効果になることがあります。
そのため介助者は、「一歩ずつで大丈夫ですよ」「ゆっくり進みましょう」といった安心感を与える声かけを心がけましょう。
また、ご利用者様自身が歩き出す「タイミング」を待つことも重要です。焦らず、呼吸やリズムに合わせて一歩が出るのを見守る姿勢が求められます。そのタイミングに合わせて「せーの」や「1、2の3」などの声かけは効果的かと思います。
②バランスを支える位置に立つ
パーキンソン病の方は、前方や横方向にバランスを崩して転びやすいのが特徴です。付き添って歩く場合は介助者はご利用者様の少し後ろ・斜め横に立ち、万が一のときにすぐに支えられる位置をとりましょう。
※介助する際は、前方から手引き歩行が必要なケースなど一概にはいえません。
真正面に立つと、ご利用者様の動きを妨げてしまったり、急な突進現象の際にぶつかってしまう危険があります。
また、介助者自身も腰や肩に負担をかけないよう、膝を軽く曲げ、いつでも支えられる体勢を意識するとより安全です。
③環境を整える
段差や障害物は、パーキンソン病の方にとって転倒の大きなリスクになります。
たとえば、カーペットの端やちょっとした段差でも、すり足歩行でつまずきやすくなるのです。
歩行前には、床の状態や通路の広さを確認し、できる限り安全に歩ける環境を整えましょう。
- 方向転換が少なくて済むように動線を整理する
- 廊下の荷物を片づけて動線を広げる
- 照明を明るくして足元を見やすくする
こうした工夫が、ご利用者様の安心感を高め、転倒リスクを大幅に下げることにつながります。
④声かけの工夫(リズムや合図を活用する)
パーキンソン病では「すくみ足」が出て足が出にくい場面がよくあります。そんなときに有効なのが、リズムや合図を使った声かけです。
「せーの」「いち、に」「右、左」など、テンポをつけると歩きやすくなる方もいます。
また、床にテープを貼って「次はここに足を置きましょう」と視覚的な合図を出すのも効果的です。
ただし、ご利用者様によって合う合図は違うため、反応を観察しながら工夫を重ねることが大切です。
⑤介助者自身の安全確保も忘れずに
歩行介助では、ご利用者様の安全ばかりに気を取られてしまいがちですが、介助者自身の体の使い方も重要です。
- 腰をかがめすぎないように膝を曲げる
- 急に体重がかかっても対応できるように足を開いて立つ
- ご利用者様が倒れそうになったら無理に支えず、ゆっくりと座らせるように介助する
介助者がケガをしてしまうと、その後のケア継続も難しくなります。ご利用者様と介助者の双方が安全でいられる方法を選ぶようにしましょう。
具体的な歩行介助の工夫
1. すくみ足への対応
すくみ足とは「足を出したいのに前に出ない」という症状で、出だしや狭い場所でよく見られます。
① リズムを与える
「いち、に」「右、左」などの掛け声や、手拍子でテンポを取ると、動きやすくなる方がいます。音楽に合わせるのも効果的です。
音楽療法でも、一定のテンポに合わせて歩行することで、自然に足が前に出やすくなることが知られています。
② 視覚的な工夫
床にテープで線を引いたり、介助者の靴先を軽く前に出して「次の足の置き場」を示すと、一歩を踏み出しやすくなります。
「ここに足を置きましょう」と具体的に指示をすると、意識が集中しやすく効果的です。
③ 体の動きを引き出す
1歩目を太ももを上に上げるように指示することで、足が前に出るケースもよく有ります。
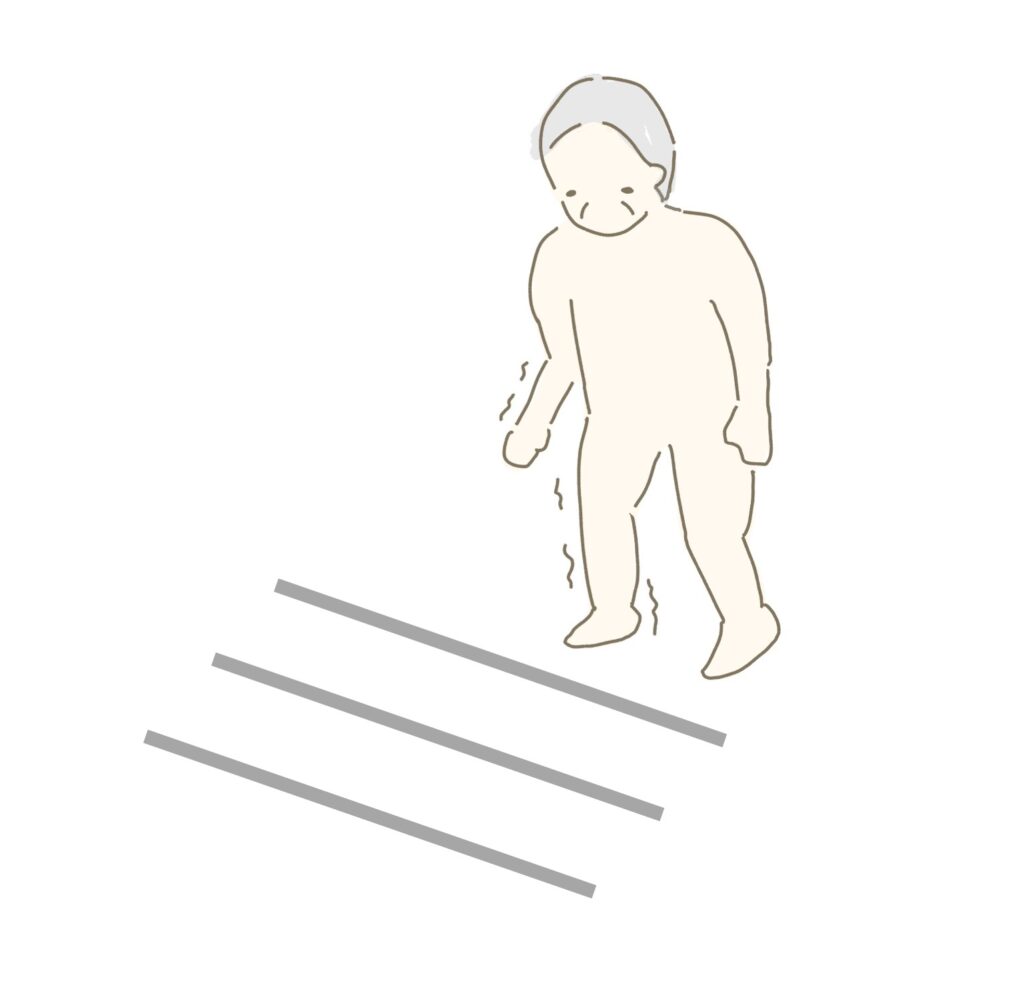
2. 小刻み歩行への対応
小刻み歩行は、歩幅がどんどん狭くなり、前傾姿勢のまま小さなステップを繰り返す歩き方です。
① 歩幅を意識させる
「歩幅を少し大きくしてみましょう」と優しく声をかけると、ご利用者様が自分の動きを修正しやすくなります。
ただし、無理に大股を求めるとバランスを崩しやすいため、「少しだけ広げる」くらいを意識するのがポイントです。
すり足の対策にもつながりますが、振り出した足の接地を踵からするように促すことも効果的です。
② 重心移動をサポート
両側から強く支えると、ご利用者様の体の動きが制限されてしまいます。
片側から支えながら「体重を右に」「次は左に」と重心移動を促すと、自然に足が出やすくなります。
場合によっては骨盤を軽く押しながら、重心移動のアシストをしてあげることで足が出やすくなります。
3. 突進現象への対応
突進現象は、前傾姿勢のまま止まることができずに前へ突っ込んでしまう症状で、転倒のリスクが非常に高い症状です。
① 介助者の位置
介助者はご利用者様の進行方向の少し横後ろに立ちます。前や横に立つとぶつかってしまう危険があるため、支えやすく安全な位置を意識しましょう。後ろから上腕を軽く介助することで、突進現象が起きた際にも止めることができます。
※突進現象が強く、転倒リスクが非常に高い場合は手引き歩行が効果的です。後述しています。
② 歩行補助具の活用
シルバーカーや四点杖を使うと、前傾姿勢の安定や歩行リズムの確保に役立ちます。
ただし、ご利用者様の筋力やバランスに合わせて適切な用具を選ぶことが大切です。
歩行器には「抑速付き」といって、スピードを抑える機能があるものもあります。そういった歩行器を使用することで突進現象を防ぐことができます。
③ 歩行を止める工夫
突進現象が強く出たときには「その場で足踏みしましょう」と声をかけると、一度動きをリセットできる場合があります。
4. 方向転換の工夫
方向転換は、すくみ足が出やすく、バランスを崩しやすい動作のひとつです。
① 大きく円を描くように回る
「体ごとゆっくり大きく回りましょう」と促すと、足が出やすくなり、転倒リスクも減らせます。
狭い場所で小さく回ろうとすると、足が床に張り付いて動かなくなりやすいです。
② 環境を整える
方向転換が必要な場所は、できるだけスペースを広く取っておきましょう。
廊下の角や居室の出入口に物を置かない工夫も重要です。
トイレまでの動線を方向転換が不要になるように、寝室を変えることも選択肢の一つです。
③ 声かけで安心感を与える
「ゆっくりで大丈夫ですよ」「一歩ずつ回っていきましょう」と声をかけ、焦らせないことが事故防止につながります。
歩行介助で困ったら
パーキンソン病のご利用者様の歩行介助では、「すくみ足」や「突進現象」など特有の歩行障害に直面することが多いと思います。介助者にとってもご利用者様にとっても、大きな負担になりやすい部分です。
私自身の現場での経験からも、前方からの手引き歩行はとても有効な方法のひとつだと感じています。下記にその理由や注意点をまとめてみます。
前方からの手引き歩行が有効な理由
1. すくみ足への対応
すくみ足の場面では、ご利用者様が「次の一歩」を出せずに止まってしまうことがあります。
前方に立つ介助者が一歩を踏み出すことで、その動きが目印となり、リズムを与えることができます。結果として足が出やすくなり、歩行の流れを作りやすくなります。
2. 重心移動を誘導しやすい
パーキンソン病の方は前後の重心移動が不十分になることがあります。
そこで前方から軽く体を誘導してあげると、自然と重心が前に移りやすくなります。転倒リスクを減らしつつ、一歩を踏み出すきっかけをつくれるのです。
3. 突進現象への安全対策
突進現象(前のめりに加速して止まれなくなる状態)は、とても危険な現象です。
しかし、介助者が前方にいれば、正面から制止することができます。後方や側方での介助では対応が難しい点でもあり、前方介助の大きな利点といえると思います、。
⚠️ 注意点
もちろん、この方法にも留意すべき点があります。
- 前方で支える分、介助者の身体的負担が大きくなる
- 特に体格差がある場合や、介助量が多い方の場合、腰や肩を痛めやすい
- 歩行器や手すりなどの環境設定を組み合わせると安全性が高まる
介助者が無理をしてしまうと、ご利用者様を守るどころか自分自身がケガをしてしまうリスクもあります。そのため「姿勢に注意する」「道具を併用する」といった工夫が大切です。
正しい手引き歩行・注意点
正しい手引き歩行のポイント
- ❌手を握って介助する → 膝折れやふらつきに対応できない
- ⭕️肘を持って支える → 急な転倒リスクにも対応でき、安全に介助できる
→「手」ではなく「肘」を支えるのが正しい手引き歩行です。
こちらのショート動画も参考にしてみてください。
▶︎手引き歩行の良い例、悪い例✨手を握って介助すると膝折れに対応できません💦肘を持って介助しましょう😊✨
環境設定の工夫
パーキンソン病の方の歩行介助では、「介助者の技術」だけでなく「歩きやすい環境づくり」が大きなカギになります。環境を整えるだけでも、転倒リスクをぐっと下げることができるます。
通路は広く確保し、物を置かない
ちょっとした段ボールやスリッパでも、パーキンソン病の方には大きな障害物になります。通路はできるだけシンプルにし、置き家具や物を減らしてまっすぐ歩ける動線を確保しましょう。
床は滑りにくい素材を選ぶ
フローリングは靴下やスリッパで滑りやすいことがあります。しかし、毛足の長いカーペットは足先が引っかかりやすく、転倒のリスクを高めます。かといってカーペットを外すと、フローリングが滑りやすくなるため注意が必要です。カーペットを使用する場合は、端を専用の画鋲などでしっかり固定して、浮きやたるみを防ぐことが大切です。
靴はすり足でも引っかかりにくいデザインを選ぶ
一般的な室内履きでは、つま先が引っかかりやすく転倒の原因になります。つま先が少し反り上がっている靴や、底がフラットで軽いタイプを選ぶと歩きやすさが大きく変わります。
トイレやベッドまでの動線に手すりを設置する
特に夜間は転倒のリスクが高まります。トイレや寝室までの通路に手すりを設けることで、安心して歩行できるようになります。立ち上がりや方向転換のしやすさも向上します。手すりの適切な配置や手すりの種類は、担当のリハビリのスタッフや福祉用具専門相談員に相談しましょう。ケアマネージャーに相談することで手配もしてくれます。
寝室の変更も考える
階段のある2階を寝室にしている場合や、トイレまで遠い、または部屋の位置や家具の配置によって方向転換が多く必要な場合は、特に夜間の移動は大きなリスクになります。可能であれば1階に寝室を移すことや、トイレの近くに寝室を移すなど、生活動線そのものを見直すことも大切です。
「環境設定=介助の第一歩」
介助者のサポートに頼るだけでなく、住環境そのものを整えることで、ご利用者様の自立度が高まり、転倒リスクも大幅に減少します。
環境を整えるだけでも、転倒リスクは大幅に減少します。
ご家族や介助者へのアドバイス
パーキンソン病の歩行介助は「知っているかどうか」で大きな差が出ます。
- 転倒リスクを減らすためには、無理に支えるよりも“環境と声かけ”
- すくみ足にはリズム、突進現象には位置取りが有効
- 小さな工夫が、ご利用者様の自立度を高め、介助者の負担も軽減する
そして何より、「できることを制限しない」ことも大切です。
安全を確保しながらも、ご利用者様自身ができる範囲を尊重し、自立した歩行を支えていくことが介助の理想です。
介助者自身の腰痛予防も大切
歩行介助は、ご利用者様を支えながら自分の体も使うため、介助者にとって腰痛リスクが高い場面です。
- ボディメカニクスを意識する(腰を曲げずに膝を使う)
- 支えるのではなく誘導する(力で支えすぎない)
- 補助具を積極的に活用する
まとめ
パーキンソン病の方の歩行介助は、ただ「体を支える」だけでは十分とはいえません。
ご利用者様に安心して歩いていただくためには、症状の特徴を理解した上で、工夫を積み重ねていくことが大切です。
- すくみ足、小刻み歩行、突進現象といった歩行の特徴を理解する
- 声かけやリズムづけを活用し、足を出しやすくする
- 環境を整えて転倒リスクを減らす
- 介助者自身の腰痛予防や安全な姿勢を意識する
こうした対応を組み合わせることで、ご利用者様の「歩ける喜び」を支えられるだけでなく、介助者にとっても安心して続けられるケアになります。
また、YouTubeチャンネルでも実演を交えて詳しく解説しています。あわせて動画を見ることでより理解が深まると思いますので、気になる方は下記のリンクからご視聴してみてください。
あわせて読みたい記事
▶︎【介護職必見】PTが教える!基本的な歩行介助
▶︎腰痛対策!腰椎サポーターおすすめ5選【プロが選ぶ】
ご利用者様にとって安全で快適な歩行を、そして介助者にとって無理のない支援を実現するために、ぜひ日々の介護に取り入れてみてください。

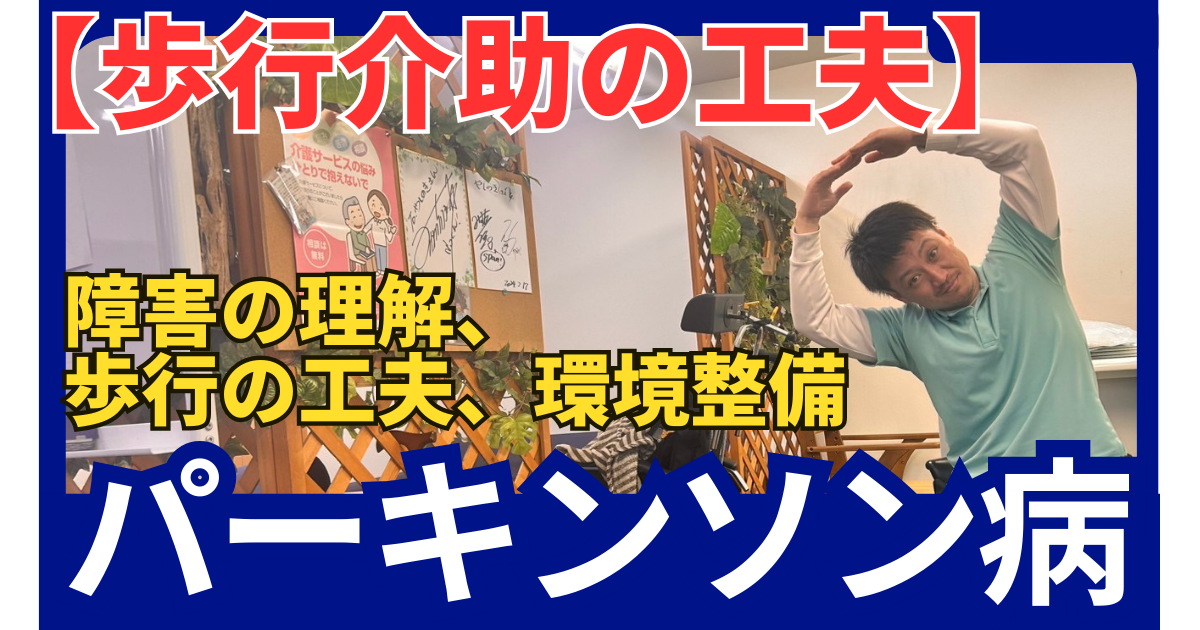

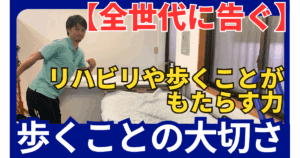
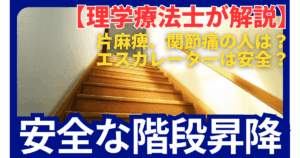
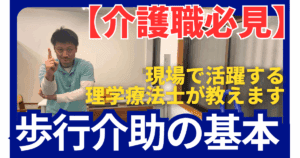
コメント