はじめに
起居動作(寝返り・起き上がり・立ち上がり)は、介護の現場で最も頻繁に行われる基本動作のひとつです。ご利用者様にとっては「ベッドから起きる」「椅子に座る」といった日常生活のスタート地点であり、自立度を左右する重要な動きです。
しかし介助の現場では、
- 「声をかけてもなかなか動いてくれない」
- 「体が重くて支えきれない」
- 「ベッドからの移動が怖いと訴えられる」
といった困りごとが多く見られます。さらに介助方法を間違えると、ご利用者様の転倒リスクや介助者の腰痛リスクにもつながります。
起居動作とは?
起居動作の基本的な意味
「起居動作」とは、寝る・起きる・座る・立つといった、日常生活を送る上で欠かせない一連の基本動作です。人が生活をするうえで「始まり」となる動きでもあり、誰にとっても自然に行っている動作ですが、加齢や病気、障害の影響によって困難になる場合があります。
特に介護現場での「起居動作」には、以下のような動きが含まれます。
- ベッド上での寝返り
- 仰臥位(あお向け)から側臥位(横向き)、そこからの起き上がり
- ベッド端での座位保持(座った姿勢の安定)
- 座位から立ち上がりなど、次の動作への移行
このように、起居動作は日常生活動作(ADL)の基盤となる部分であり、ここがスムーズにできないと、食事・排泄・移動など他の活動にも支障が出てしまいます。つまり、「生活のすべての始まり」といえる動作なのです。介助方法を誤れば、ご利用者様の自立度の低下を招き、転倒や怪我のリスクも高まります。

起居動作の介助の目的
起居動作の介助は、単に「ベッドから起こしてあげること」ではありません。大切なのは、以下の2つの視点です。
- ご利用者様の残存機能を最大限に引き出すこと
- ご本人ができる部分はできるだけ自分で行っていただくことが、自立支援につながります。
- 例えば、手すりをつかむ、足を床につけるといった小さな動作でも「自分でできた」という感覚は生活の意欲を高めます。
- 介助者の体に負担をかけず安全に支援すること
- 起居動作は一日に何度も繰り返されるため、間違った介助方法は介助者の腰や肩を痛める原因になります。
- 正しい姿勢やボディメカニクスを上手く利用すること、福祉用具を活用することで、ご利用者様も介助者も安心できる介助が可能になります。
この2点を意識することで、ご利用者様には達成感や安心感が生まれ、介助者は職業病ともいえる腰痛を防ぐことができます。まさに、双方にとってメリットのある介助が「起居動作介助」の本来の目的といえるのではないでしょうか。
起居動作の介助でよくある困りごとと解決法
① 声をかけても動いてくれない
よくある原因
- 「起きましょう」といった抽象的な声かけで動作のイメージができない
- 不安や恐怖心が強く、体が固まってしまう
- 聴覚障害や認知症の影響で、指示が理解しにくい
解決法の例
- 具体的な声かけをする
- 「右手でベッド柵を握ってください」
- 「左足を床につけましょう」
- 視覚的な合図を加える
- 指差しやジェスチャーで伝える
- 触覚で安心を与える
- 肩や腕に軽く触れ、「一緒にやりましょう」と伝える
- また無理やり介助するのではなく、アシストするように介助していくことで、ご自身で動いてくれるケースもあります。
- 実演して見せる
- 介助者が先に動作を行い、動きをイメージさせる
👉 「声かけ+実演+触覚サポート」を組み合わせることで、ご利用者様が安心して動き出しやすくなります。
② 体が重くて支えきれない
よくある原因
- 介助者が腕力だけで引き起こそうとする
- ベッドの高さが低すぎて、介助者が前かがみになりやすい
- 布団やマットレスの摩擦が大きく、ご利用者様が動きにくい
解決法の例
- ベッドの高さ調整
- 介助者の腰の位置に合わせてベッドを上げる
- これだけで介助者の負担は大幅に軽減されます
- 福祉用具の活用
- スライディングシートや介助シートを使用して摩擦を減らす
- 手すりを活用して自力で起き上がれるよう促す
- 残存機能を活かす声かけ
- 「足を床にしっかりつけましょう」
- 「両手で柵を持って起き上がってみましょう」
👉 「持ち上げる介助」ではなく「ご本人の動きを引き出す介助」を意識することが大切です。
③ ベッドからの移動が怖い
よくある原因
- 体幹や下肢の筋力低下によりバランスを崩しやすい
- 脳梗塞などの疾患によってバランスが取れない
- 過去に転倒経験があり、恐怖心が強い
- 床やベッド周囲の環境が不安定
解決法の例
- 座位では、足をしっかり床につけて安定させる
- 足底が床につくと安心感が増し、バランスも取りやすい
- 補助具の活用
- 座位保持用のクッションや介助ベルトを使用
- 声で安心感を与える
- 「私が横にいますから大丈夫ですよ」
- 「一緒にやりましょう」
- 「急がずゆっくり動きましょう」
👉 不安を減らすだけで、ご利用者様の動きはスムーズになります。

よくある間違った介助と正しい方法
起居動作の介助は、ちょっとしたコツを知っているかどうかで大きな差が出ます。特に「腕を引っ張る」「中腰で支える」といった方法は、一見すると簡単に思えても、ご利用者様にも介助者にも大きな負担をかけてしまいます。ここでは、介護現場でよく見られる間違った介助と、正しい介助方法の違いを解説します。
腕を引っ張る介助の危険性
ベッドから起き上がるとき、ご利用者様の腕を引っ張って起こそうとする介助はありがちな方法ですが、実は非常に危険です。
- 肩関節を痛めるリスク
ご利用者様の肩関節は加齢や病気により柔軟性が低下しているため、腕を強く引っ張ると脱臼や炎症を引き起こすことがあります。特に麻痺のある腕を引っ張ることは脱臼のリスクがかなり高いです。 - 介助者自身も腰を痛めやすい
腕を引く動作は腕や腰に大きな力をかけるため、繰り返すうちに腰痛の原因になります。
👉 「とりあえず起こせる」方法に見えても、実は双方にとってリスクが大きい介助方法です。
腰を痛めやすい介助者の動作例
介助の際に腰を痛める原因は「姿勢」と「力の使い方」にあります。特に次のような動作は要注意です。
- 中腰のまま支える
腰を曲げたまま力を入れると、腰椎に大きな負担がかかります。 - 腕の力だけで持ち上げる
人の体を腕の力だけで支えるのは限界があり、肩や腰を痛める原因になります。 - ご利用者様の動きを待たず、先に引っ張る
ご利用者様の動きに合わせずに力任せに引くと、介助者は腰に負担を集中させることになり、痛めやすくなります。
👉 「腰に負担のかかる介助」は、介助者にとって最も危険なパターンです。
安全に支えるコツ(ボディメカニクスをしっかり意識)
介助は「力で持ち上げる」ものではなく、「体を使って自然に支える」ものです。ボディメカニクスを活用することで、ご利用者様も介助者も安全に動作できます。
- 足を広げて自分の重心を安定させる
支える基盤を広くすることで、ちょっとした揺れにも対応しやすくなります。 - 腰ではなく膝や股関節を曲げて体を使う
腰を曲げるのではなく、膝を曲げてしゃがむようにすると、腰への負担が大きく減ります。 - 体重移動で自然に支える
腕の力ではなく、自分の体の重心移動を使うと、少ない力で支えられます。
👉 「力で持ち上げる介助」ではなく、「体を使って支える介助」が正解です。
「ボディメカニクス」の内容はこちらの記事でしっかり書いていますので、詳しく知りたい方は、下記のリンクから読んでみてください。
▶︎介護技術を極める!ボディメカニクスの基本と実践
まとめると、正しい介助は「ご利用者様の動きを引き出すこと」と「介助者が自分の体を守ること」の両立です。日々の小さな意識が、ご利用者様の安心と介助者の健康につながります。。

介助者の負担を減らすための工夫
起居動作の介助では、ご利用者様の安全を守ることと同じくらい、介助者自身の体を守ることも大切です。無理な姿勢や力任せの介助を続けていると、腰痛や肩の痛みといった職業病につながってしまいます。ここでは、介助者の負担を軽減するための工夫を紹介します。
環境設定を優先する
介助を始める前に、まずは「環境を整える」ことが基本です。
- ベッドの高さを調整して、自分の腰の位置に合わせる
- 通路を確保して、動作の妨げになる物を置かない
- 動線を整理し、ご利用者様が起き上がった後の動きをスムーズにする
👉詳しくはこちらの記事にまとめています。
▶︎介護技術で一番大事なこと、それは“環境設定”だった
福祉用具を積極的に使う
「人の力だけ」で介助を行う必要はありません。福祉用具を上手に活用することで、ご利用者様にも介助者にもやさしい介助が可能になります。
- 介助シート(スライディングシート):摩擦を減らして楽に体を動かせる
- 手すり:自分で支えられるため、介助の負担が大幅に軽減
- 介助ベルト:しっかりと支えやすく、転倒防止にもつながる
「使えるものは使う」という発想が、腰痛予防にもご利用者様の自立支援にもつながります。
腰痛予防を意識する
介助者の健康を守るために、日頃から腰痛対策を意識することが欠かせません。
- ボディメカニクスを常に実践し、腰ではなく脚や体幹で支える
- 無理な力で支えないよう、ご利用者様の残存機能を引き出す
- 腰痛予防グッズ(コルセット・サポーター・インソールなど)を活用して、日々の負担を軽減
- セルフケアも大切です
👉記事にもまとめています。よろしければ参考にしてみてください。
▶︎腰痛予防・対策の記事を読む
まとめ
起居動作の介助は、ご利用者様にとって「一日のスタート」であり、介助者にとっては「最も多く関わる動作」のひとつです。
- 声かけは具体的に
- 環境設定で動きやすさをサポート
- 福祉用具を取り入れて介助者の負担を減らす
- 力任せではなく、ボディメカニクスで支える
こうした工夫を積み重ねることで、ご利用者様は安心して動作でき、介助者も腰痛などを防ぎながら安全に支援を続けられます。
起居動作に関する内容は、私のYouTubeチャンネルでも実演を交えて解説しています。文章だけでは伝わりにくい部分もありますので、ぜひ動画もあわせてご覧ください。
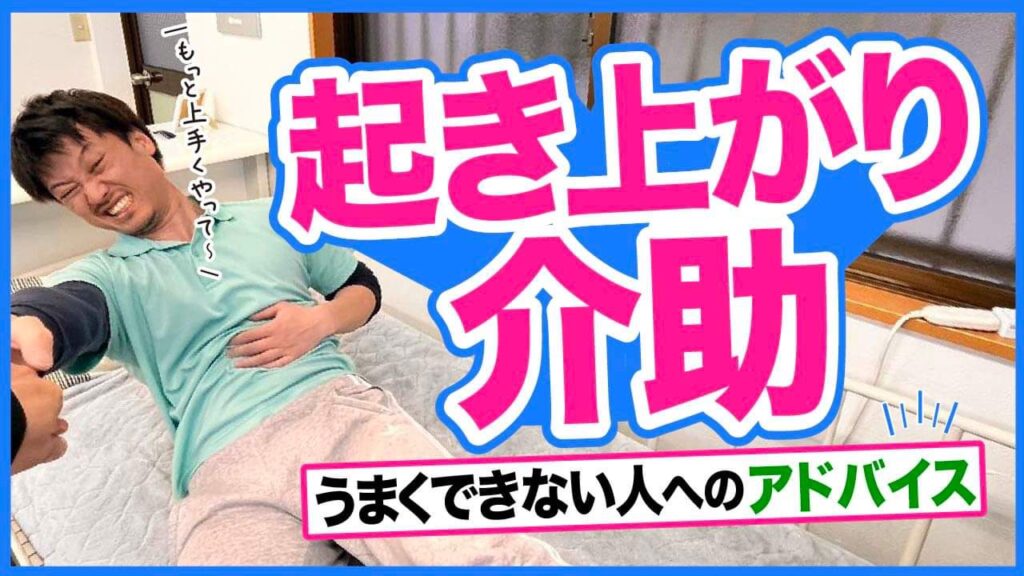
あわせて読みたい記事
▶︎介護技術で一番大事なこと、それは“環境設定”だった
▶︎介護技術を極める!ボディメカニクスの基本と実践
▶︎起き上がり動作(起居動作)の基本的な介助方法

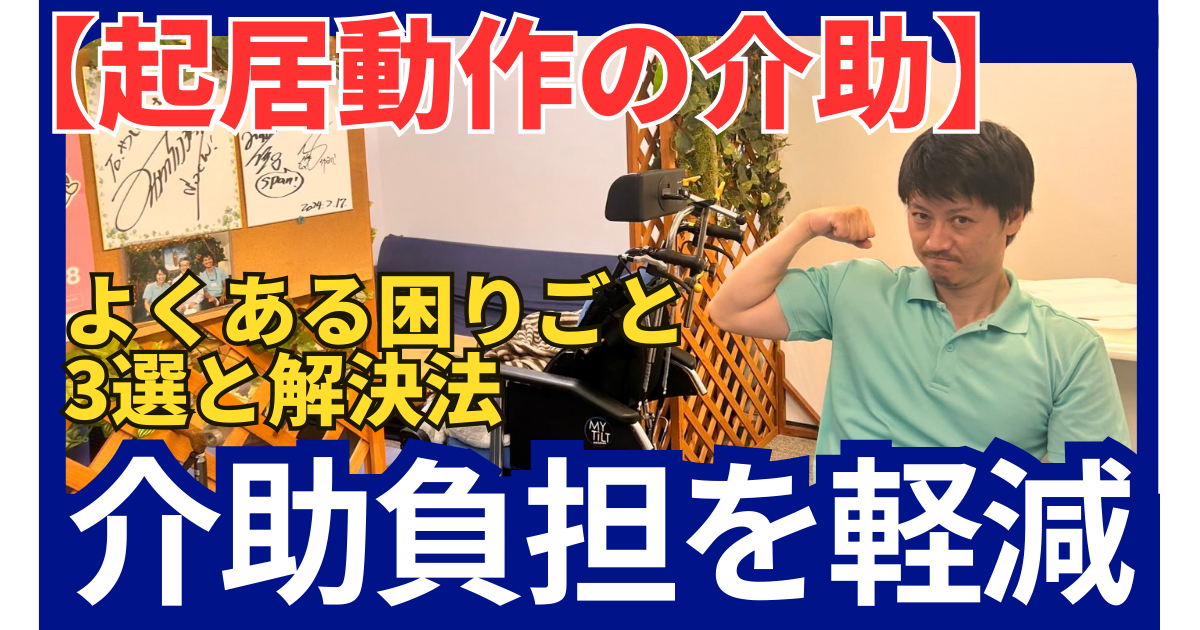

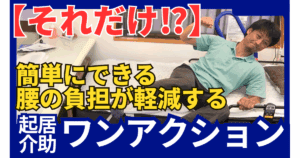
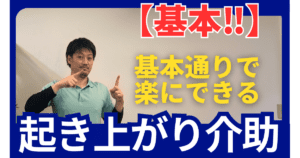
コメント