はじめに
介護の仕事は、人の命や生活に直接関わる、とても責任の大きい仕事です。
日々の業務の中で行う一つひとつの判断や行動が、ご利用者様の安全・健康・生活の質に直結します。
だからこそ、小さなミスであっても、その影響は想像以上に大きくなることがあります。
たとえば、ちょっとした確認漏れが転倒事故につながったり、申し送りの情報不足が誤ったケアを招いたり。その結果、残念なことにご利用者様だけでなく、ご家族様やチーム全体との信頼関係にもヒビが入ってしまうこともあるのです。
しかし、介護現場は常に慌ただしく、突発的な対応が求められる場面も多いのも現実です。
食事介助や入浴介助、記録や申し送りなどを並行して行う中で、「つい忘れてしまった…」「気づいたらやってしまった…」という“うっかりミス”は、どんなに経験豊富な介護職員でも避けきれないことがあります。
大切なのは、「絶対にミスをゼロにする」ではなく、「ミスを限りなく減らす習慣を持つ」ことだと私は思います。
なぜ“うっかりミス”が起きてしまうのか?
介護現場のミスは、単純な「不注意」だけが原因ではありません。
多くの場合、「環境要因」+「心理的要因」+「身体的要因」が複雑に絡み合って起こります。
1.環境要因
- 人手不足で1人あたりの業務量が多く、常に時間に追われている
- 設備や動線が使いづらく、ちょっとした移動や準備にも手間がかかる
- 情報共有の場や方法が限られ、申し送りがスムーズに行われない
こうした環境では、「確認してから動く」余裕そのものが削られます。
例えば「すぐに移乗してほしい」と急かされ、ベッド周りの整理をせずに移乗し、転倒のリスクが高まる…といったことは、実際の現場でよく起こります。
2.心理的要因
- 「いつもやっているから大丈夫」という過信や慣れ
- 利用者さんを待たせてはいけないという焦り
- 上司や同僚から「早くして」と言われるプレッシャー
心理的な要因は、“確認作業を省略してしまう”一番の理由です。
本来であれば薬の量や名前をダブルチェックする場面でも、「これで合っているはず」と思い込み、確認を飛ばしてしまう。
その結果、小さな「うっかり」が大きな事故につながることもあります。
3.身体的要因
- 夜勤や連勤による疲労、睡眠不足で集中力が低下
- 腰痛や肩こりなど慢性的な痛みによって動作が雑になる
- 食事を抜く、休憩を取れないことでエネルギー不足に陥る
介護は体力を消耗する仕事です。
体調が万全でなければ、注意力や判断力も落ちていきます。
「もう少し頑張れば大丈夫」と無理を重ねることが、結果的に事故のリスクを高めてしまうのです。
まとめると…
介護現場での“うっかりミス”は、ただの「気のゆるみ」ではありません。
忙しさや焦りといった心理的プレッシャーに加えて、働く環境の不備や体調管理不足といった複数の要因が重なって生じます。
だからこそ、ミスを減らすためには 「個人の注意力」だけに頼るのではなく、仕組みや環境を整えることが不可欠です。
- 余裕を持った人員配置
- 確認を促すチェックリストや掲示物
- 職員が休める体制づくり
こうした職場全体での工夫が、介護の安全性を大きく高める第一歩となります。
しかし現実には、理想通りに体制を整えられない職場も少なくありません。
- 人員不足で休憩やシフト調整が難しい
- 設備投資や環境改善は「会社がしてくれない」と進まない
- 忙しさの中で「チェックリストやルールづくり」が形骸化してしまう
つまり「分かってはいるけど、なかなか実現できない」という葛藤を、多くの介護職が抱えています。
だからこそ、現場の一人ひとりができる“小さな工夫”を積み重ねることが大切です。
たとえ職場全体の改善が進まなくても、自分やチームで取り入れられる工夫を実践するだけで、ミスのリスクはぐっと減らすことができます。

うっかりミスを減らす習慣5つ
介護現場で起こる“うっかりミス”は、ほんの数秒の油断や確認不足から生まれます。
ここでは、特に多い5つのケースと、今日からできる予防習慣をご紹介します。
1.転倒防止のための環境チェック
よくあるミス
- 移動時に足元の物を片付け忘れ、つまずきの原因になる
- 電気コードや段差を見落とし、ヒヤリとする場面が発生
予防策
- 介助前に必ず「床・足元・手元」を確認する習慣をつける
- 特に移乗や歩行介助の前には30秒の環境確認を徹底する
(ベッドの高さ、車椅子や歩行器の位置、ご利用者様の足の位置など)
▶︎この記事も併せて読んでみて下さい
介護技術で一番大事なこと、それは“環境設定”だった
ポイント
2.口頭伝達だけに頼らない
よくあるミス
- 申し送りを口頭だけで行い、情報が抜け落ちる
- 「聞いたつもり」だったが、細かい注意点を忘れてしまう
予防策
- 必ず書面や電子記録で残す
- 必ず情報収集を怠らない
- 緊急時以外は「口頭+記録」をセットにする
ポイント
3.“慣れ”による油断
よくあるミス
- 毎日見ているご利用者様の動作を過信し、介助が雑になる
- 「いつもできているから今日も大丈夫」と思い込む
予防策
- 毎回の動作を「初めて見るつもり」で観察する
- 小さな変化にも敏感に気づけるよう意識する
- 今日の体調など聞くようにする
- コミュニケーションをとり、いつもと比べて元気があるのかないのかなど、細かいところにも気を配る
ポイント
4.薬の取り扱いミス
よくあるミス
- 配薬時に確認を省略し、別の人の薬を渡してしまう
- 薬の量や種類を間違える
予防策
- 配薬は必ず「名前・薬・量」を指差し確認する
- 途中で作業を中断された場合は、最初から確認し直す
ポイント
5.自分の体調管理を軽視する
よくあるミス
- 疲労や腰痛を放置し、介助中にケガをする
- 睡眠不足や集中力低下で判断ミスを起こす
予防策
- 休息・ストレッチ・正しいボディメカニクスを習慣化する
- 体調不良時は無理せず早めに相談する
▶︎腰痛予防の記事も書いています。よかったら併せて読んでみて下さい
腰痛対策
ポイント

まとめ:小さな習慣が安全な介護をつくる
介護現場での“うっかりミス”は、決して「個人の不注意」だけが原因ではありません。
環境の不備や心理的プレッシャー、身体的疲労など、複数の要因が重なって起こるものです。
理想的には、マンパワーの増強や設備改善など、会社全体での環境整備が重要ですが、現実には「人手不足で休憩やシフト調整が難しい」「設備投資や環境改善が進まない」といった職場も少なくありません。
そんな中でも、個人やチームでできる工夫や習慣は多くあります。
小さな確認や観察、記録の徹底を日々意識することで、ミスのリスクはぐっと減り、ご利用者様の安全と安心につながるのです。
今回ご紹介した5つの習慣を意識するだけでも、介護の安全性は大きく変わります。
- 介助前の環境チェックで転倒リスクを減らす
- 口頭だけでなく記録で残すことで情報の抜け漏れを防ぐ
- 毎回「初めて見るつもり」で観察力を高める
- 薬は必ず指差し確認して安全を守る
- 自分の体調管理を習慣化し、事故を未然に防ぐ
どれも難しいことではなく、今日からすぐに取り入れられる小さな工夫ばかりです。
また、チームで声を掛け合い、確認し合う文化を作ることも、個人だけでは防げないミスを減らす大きな力になります。
安全な介護は、一日にして成らず。
毎日の積み重ねが、チーム全体の信頼とご利用者様の笑顔を守る力になるのです。
小さな習慣を一つずつ意識して取り入れることで、現場は確実に、そして着実に安全な場所になっていきます。
あわせて読みたい記事
一緒に見たいYouTube動画
【環境設定が1番大事】介護の負担や事故を減らすために大切なこと



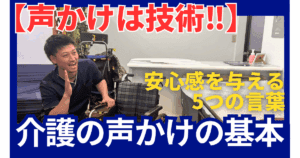
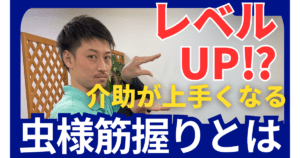
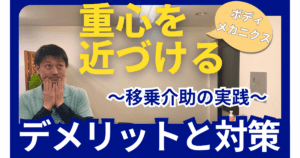
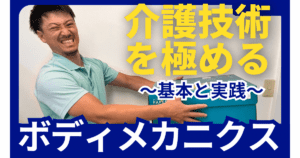
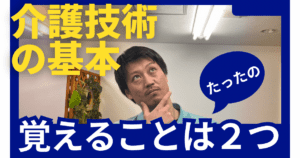
コメント