はじめに
今、日本の介護業界は深刻な「慢性的な人手不足」に直面しています。
少子高齢化の加速とともに、介護施設や在宅サービスの需要は年々高まり、全国の介護施設の数も増加傾向にあります。
一方で、介護に従事する人材の確保が追いつかず、現場では常に人手が足りない状況が続いています。
「人が足りなくて十分なケアが行き届かない」「離職者が出ても、すぐに補充できない」といった切実な声が、全国の現場から上がっており、残された職員の業務負担は増すばかりです。
その結果、身体的・精神的な疲労からさらに離職者が増え、悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。
この記事では、介護業界における人材不足の現状とその背景、そして現場に立つ私たちにできる対策について、実際の経験をもとにわかりやすく解説していきます。
介護業界で働くすべての人にとって、今の状況を見つめ直す一助になれば幸いです。
介護業界の人材不足はなぜ起きているのか?
介護業界では深刻な人材不足が続いています。その原因は一つではなく、社会構造や働く環境、業界のイメージなど複数の要因が絡み合っています。ここでは主な3つの要因を解説します。
①超高齢社会の進行
日本は世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいます。
厚生労働省によると、2040年には高齢者(65歳以上)が総人口の35%を超えると予測されています。
この急激な高齢化によって、要介護者の数は今後ますます増加すると見込まれています。
それに伴い、介護サービスの需要も爆発的に増えていく一方で、それを支える介護人材の確保が追いついていないのが現状です。
高齢化の進行は避けられない社会の流れであり、介護業界の人手不足は今後さらに深刻化していくと考えられます。
🌍世界の高齢化率比較(2024年推計)
| 国名 | 総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(65歳以上) | 備考・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 約124,000 | 約36,000 | 29.0% | 世界最高水準の高齢化率 |
| 🇮🇹 イタリア | 約58,800 | 約14,600 | 24.8% | ヨーロッパで最も高齢化が進む国の一つ |
| 🇩🇪 ドイツ | 約83,200 | 約18,800 | 22.6% | 労働力不足が社会問題に |
| 🇫🇷 フランス | 約68,000 | 約13,500 | 19.9% | 社会保障制度に大きな負担 |
| 🇬🇧 イギリス | 約67,000 | 約12,600 | 18.8% | 少子高齢化が緩やかに進行 |
| 🇰🇷 韓国 | 約51,700 | 約9,800 | 18.9%(急増中) | 2050年には日本を超える予測も |
| 🇨🇳 中国 | 約1,409,000 | 約204,000 | 14.5% | 今後急激な高齢化が懸念される |
| 🇺🇸 アメリカ | 約333,000 | 約57,000 | 17.1% | 移民の影響で相対的に若い人口構成 |
| 🇧🇷 ブラジル | 約216,000 | 約20,000 | 9.3% | 高齢化はこれから進行 |
| 🇮🇳 インド | 約1,428,000 | 約98,000 | 6.9% | 世界最多人口も高齢化率はまだ低い |
🔍 ポイント
- 日本は高齢化率29.0%で世界一。2040年には35%以上に達する見込み。
- 韓国は高齢化のスピードが速く、将来的には日本を上回ると予測されている。
- 先進国ほど高齢化率が高い傾向にあり、医療・年金・介護など社会保障の課題が深刻。
- インドやブラジルなどの新興国では、今後数十年かけて高齢化が進むと予測されている。
②離職率の高さ
介護職は「離職率が高い職種」としても知られています。
離職率とは、1年間でどれくらいの人が職場を辞めたかを示す指標で、
「離職者数 ÷ 平均在籍者数 × 100」で計算されます。
例えば、年間に20人が辞め、平均在籍者が95人だった場合、離職率は約21%となります。
厚生労働省のデータによると、介護職の年間離職率は約15%前後で推移しており、他産業と比較しても高水準です。
※ちなみに離職率が最も高い、宿泊業・飲食サービス業は約 26.6〜26.8%、離職率の低い鉱業・採石業・砂利採取業では、約 3.8〜6.3%だそうです。
主な離職理由としては、以下のような点が多く挙げられます。
- 身体的・精神的な負担の大きさ
介護業務による腰痛・肩こりなどの身体的負担や、認知症のご利用者様への対応など精神的負担が大きく、長期間続けにくいのが現状にあります。 - 給与の低さや待遇面への不満
仕事の責任や負担に比して、報酬が見合っていないと感じる人が多くいており、特に他産業と比較した際に「報われない仕事」という印象がつきやすい点も問題です。実際にそう感じている人も多いように感じます。
介護保険制度をはじめとする国の予算によって報酬が定められているため、待遇面の改善が難しいという背景もあります。 - 人間関係のストレス
職場内の人間関係、ご利用者様・ご家族とのやり取りなど、対人ストレスが多く、うまくいかないことで辞めてしまうケースも少なくありません。 - スキルアップやキャリア形成の限界
資格を取っても昇給や役職に反映されづらい職場もあり、「将来が見えない」と感じる若い世代の離職にもつながっています。
③若手人材の参入が少ない
介護業界には、若年層や異業種からの転職希望者が集まりにくいという構造的な問題があります。
その背景には、いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)」といったマイナスイメージが根強く存在しています。
- 仕事がきつい(体力・気力ともに負担が大きい)
- 汚い(排泄介助や清掃業務への抵抗感)
- 危険(感染症や事故のリスク)
このようなイメージがあるため、「最初から介護職を目指さない」「一度経験しても長続きしない」といった傾向が見られます。
また、どの業界にも言えることかもしれませんが、少子化の影響で若年層そのものが減少していることも、構造的な人手不足に拍車をかけています。
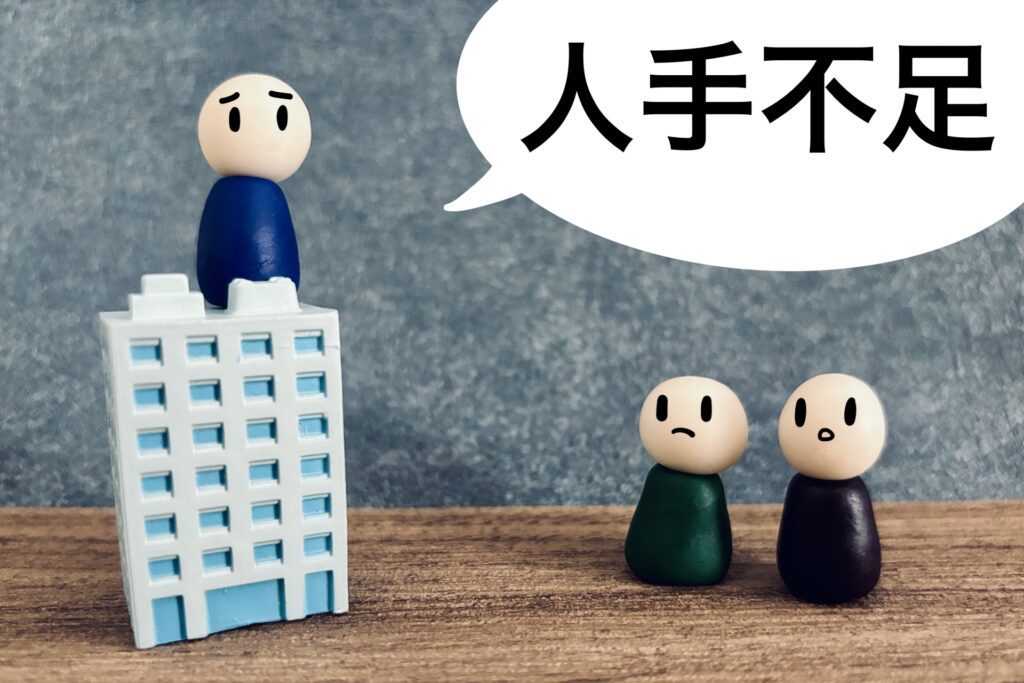
現場では今、何が起きているのか?
現在、多くの介護現場では、次のような深刻な問題が日常的に起きています。
- ご利用者様の人数に対して介助者の人数が足りないという状況が常態化
人手が明らかに足りておらず、職員一人にかかる負担が非常に大きくなっています。目が行き届かないことで、ご利用者様への対応が遅れたり、ケアの質が低下するリスクも高まります。 - 休憩時間もままならず、連勤が続く
慢性的な人手不足により、シフトに余裕がなく、職員が十分に休息を取れないケースが多く見られます。心身ともに疲弊し、モチベーションや集中力の低下につながっています。 - 書類業務に追われ、本来のケアに割く時間が減少
記録業務などの書類業務も多く、他にも請求業務や加算算定などでパソコンに向かう時間が長くなり、ご利用者様と関わる時間が削られています。「何のためにこの仕事をしているのか」と悩む職員も少なくありません。 - 経験の浅いスタッフが、いきなりリーダーを任される
本来であれば段階的にスキルアップしながら役割を担うべきところ、スタッフ不足のため、まだ十分な経験を積んでいない職員に現場のリーダーを任せざるを得ない状況もあります。
また、リーダーのみならず、研修や教育を受けないままに現場に放り出される新人もいるとよく耳にします。
解決に向けた取り組みとは?
人材不足の問題を放置すれば、現場の崩壊やサービスの質の低下にもつながりかねません。だからこそ、今さまざまなレベルでの取り組みが始まっています。
①働き方改革の推進
近年、国や自治体も本格的に介護現場の業務負担軽減に取り組んでいます。
- 介護ロボットやセンサーの導入により、見守り・移乗・排泄ケアなどの負担を軽減
- ICT(情報通信技術)の活用によって、記録業務の簡素化や情報共有のスピードアップ
- 夜勤体制やシフトの見直しにより、働きやすい職場環境づくりを推進
②賃金・待遇の改善
介護職員の給与については、処遇改善加算やベースアップ加算などにより、段階的な引き上げが図られています。
実際に「少し給与が上がった」と感じている職員もいますが、現場ではまだまだ次のような声が少なくありません。
- 「他業種と比べるとまだ低い」
- 「加算がきちんと現場職員に分配されていない」
- 「非正規と正職員で差が大きすぎる」
③働きがいのある職場づくり
給与や労働時間だけでなく、「この職場で働き続けたい」と思える環境づくりも非常に重要です。
- 利用者やご家族からの「ありがとう」が直接聞ける
- チームの一員として役に立っている実感がある
- 成長できる場や、努力が報われる評価がある
こうした“小さなやりがいの積み重ね”が、職員の心を支えます。
また、キャリアアップ支援(資格取得支援、実務者研修等)やOJT体制の充実も、若手職員の定着やモチベーション向上に直結します。
番外:技術面・健康面での負担軽減には、継続的な学びがカギ
特に介護技術や身体の使い方(ボディメカニクス)は、日々の業務負担や腰痛リスクの軽減にもつながります。
当ブログやYouTubeチャンネルでは、介護負担が軽減するように、介護技術を発信していたり、腰痛が少しでも緩和するように腰痛対策のグッズの紹介や、簡単にできる腰痛体操などをわかりやすく発信しています。
ぜひ、空き時間にのぞいてみてください。皆様の現場が少しでも楽になるヒントが見つかるはずです。
まとめ
介護業界の人材不足は、一時的な問題ではなく、少子高齢化による“構造的な課題”です。
今後ますます高齢者の数は増える一方で、現役世代の労働人口は減少し、介護を必要とする方に対して、介護を担う人の数が圧倒的に足りなくなる時代がやってきます。
このままでは、介護が必要な方がいても「受けられない」「選べない」「質が落ちる」といった深刻な状況が広がることが予想されます。
介護の“質”も“量”も守っていくには、業界全体で本気で取り組まなければなりません。
しかし、解決の糸口は決して一つではありません。
働き方の見直しやICTの活用、外国人材の受け入れ体制づくり、給与・待遇の改善、教育・研修の充実など、現場・経営・行政のそれぞれが持つ役割を果たしていくことで、未来は変わります。
また、現場の私たち自身も「人手がない」「キツい」と嘆くだけではなく、小さくてもできることから一歩ずつ行動していくことが求められます。
たとえば、職員同士が気軽に意見を言い合える風通しのよい職場づくりや、成長を感じられる教育体制、子育てや介護を両立できる柔軟な働き方の導入など、「できること」はまだまだあります。
私たち現場の職員、経営者、行政、そして社会全体が、「誰もが安心して老後を迎えられる社会」の実現に向けて、介護を支える人材の確保と育成に本気で向き合っていくことが大切だと思う今日この頃です。
それが、未来の介護を守るための確かな第一歩だということです。

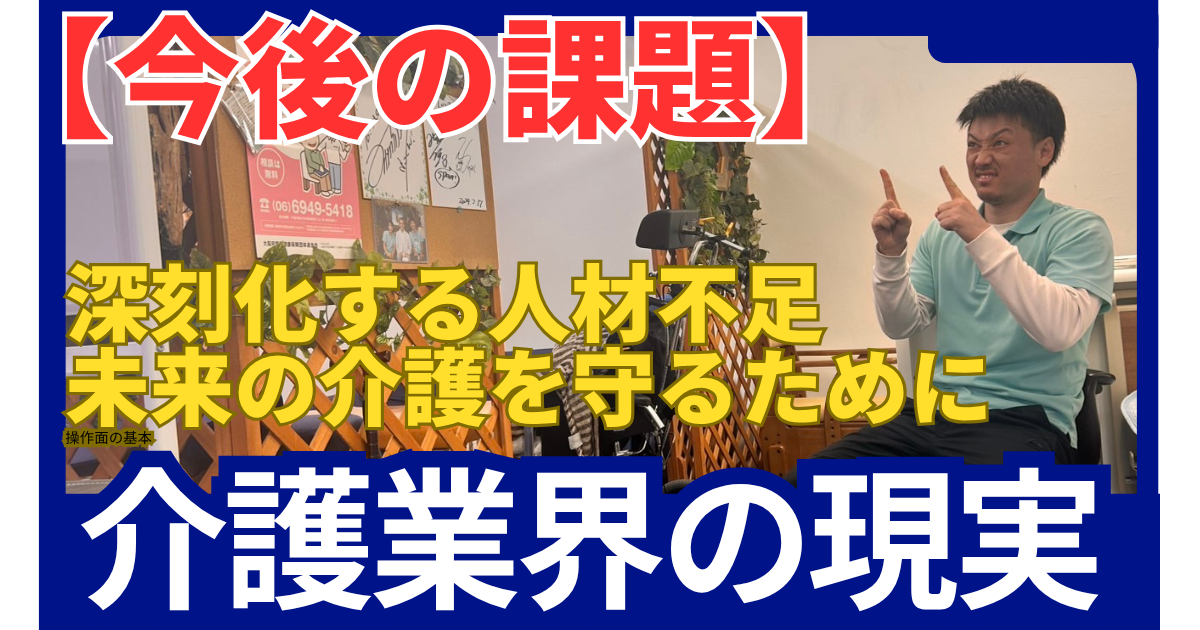

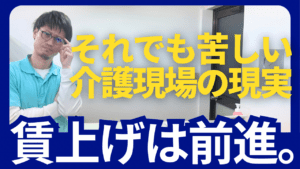
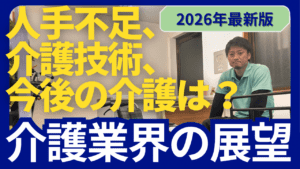
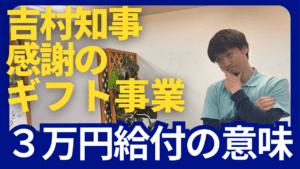
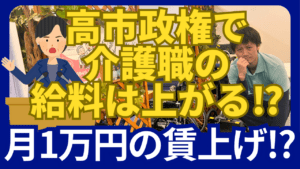
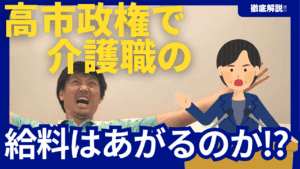
コメント