はじめに
高齢者や障がいを持つ方の生活を支えるための道具には「福祉用具」と「介護用品」があります。これらは混同されることが多いですが、それぞれ目的や定義、使用用途が異なります。
福祉用具は、自立支援や介護負担の軽減を目的とした長期間使用する機器や設備を指し、介護保険の適用を受けられる場合があります。一方、介護用品は、介護を補助し生活を快適にするための日常的な消耗品や道具であり、基本的に介護保険の適用外となります。
本記事では、福祉用具と介護用品の違いについて詳しく解説し、どのように選べばよいのか、そのポイントについても触れていきます。適切な道具を選ぶことで、ご利用者様の生活の質(QOL)の向上や介護者の負担軽減につながるため、ぜひ参考にしてください。
福祉用具とは?
福祉用具とは、高齢者や障がい者が日常生活を円滑に送るために使用する道具や設備のことを指します。
福祉用具には、移動をサポートするもの、排泄・入浴を補助するもの、介護者の負担を軽減するものなど、さまざまな種類があります。主に介護保険の適用対象となるものが多く、一定の条件を満たせばレンタルや購入補助を受けることができます。
福祉用具の主な種類とその役割
1. 移動をサポートする用具
高齢者や障がいを持つ方が安全に移動できるようにサポートする道具です。
- 車椅子:歩行が困難な方の移動をサポートするための椅子。自走式、介助式、電動式などがある。
- 歩行器:体を支えながら安定して歩くための補助具。固定型やキャスター付きなど種類が豊富。
- 杖:片足に負担がかかる方や、バランスをとるのが難しい方の歩行をサポートする。一本杖、四点杖などがある。
- スロープ:段差や階段の昇降をスムーズにするための傾斜板。車椅子利用者や歩行が不安定な方の移動を助ける。
2. 排泄や入浴を補助する用具
トイレやお風呂の動作を助けることで、QOL(生活の質)を向上させる道具です。
- ポータブルトイレ:寝室やベッドサイドに設置できる移動式トイレ。夜間やトイレまでの移動が難しい方に便利。
- シャワーチェア:浴室内で座ったまま体を洗うことができる椅子。高さ調整や背もたれ付きのものもある。
- 浴槽台:洗い場の高低差を補ったり、浴槽内で座るための台。入浴時の転倒防止や、安全な立ち上がりをサポートする。
- 手すり:トイレ・浴室・廊下・玄関などに設置し、立ち上がりや移動をサポートする。固定式や取り外し可能なものがある。
3. 介護者の負担を軽減する用具
介護を行う家族や介助者の負担を軽減し、効率よく安全なケアを提供できる道具です。
- 介護用ベッド(特殊寝台):高さ調整や背上げ・脚上げ機能がついたベッド。介護を受ける方の寝起きや移乗をスムーズにしたり、介助者の負担を軽減してくれる。
- 移乗補助具(リフトなど):ベッドから車椅子への移動などをサポートする機器。電動式やスライディングボードがある。
- 介護用エアマット:体圧を分散し、床ずれ(褥瘡)を予防するマットレス。寝たきりの方に適している。
4. 利用者の身体を保護する用具
転倒や褥瘡(床ずれ)のリスクを軽減し、安全に生活できるようにする道具です。
- 褥瘡(床ずれ)予防マットレス:寝たきりの方の皮膚を保護し、血流を促進する特殊なマットレス。
- 介護用クッション:ポジショニング・体位交換の際に使うクッションや、車椅子に座っている際に座位を安定させたり、体圧分散してくれるクッションがある。
介護保険と福祉用具の関係
福福祉用具は、介護保険の「福祉用具貸与(レンタル)」や「特定福祉用具販売(購入)」の対象となる場合があります。介護保険を利用すれば、要介護認定を受けた方が自己負担を抑えながら必要な福祉用具を使用することができます。
福祉用具貸与(レンタル)の対象
福祉用具の中でも、長期間使用することが想定されるものはレンタルの対象となります。例えば、以下のようなものが該当します。
- 歩行器
- 車椅子(自走式・介助式・電動)
- 介護用ベッド(特殊寝台)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症老人徘徊感知機器
- 手すり(工事不要で取り外し可能なもの)
- スロープ(屋内外の段差解消のためのもの)
※2024年度の介護保険改定により、購入も可能になったものもある。
特定福祉用具販売(購入)の対象
衛生的な管理が必要で、長期間のレンタルに適さないものは、購入の対象となります。例えば、以下のような用具です。
- ポータブルトイレ
- 入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽台など)
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
2024年度の介護保険改定と歩行器の変更点
2024年度の介護保険改定により、歩行器はレンタルだけでなく購入も可能となりました。これにより、利用者の状況に応じて柔軟に選択できるようになりました。ただし、以下の点に注意が必要です。
タイヤ付きの「歩行車」や「シルバーカー」は、購入の際は介護保険の対象外です。これらは歩行補助具ではなく、移動を補助する道具とみなされるため、保険適用外となります。
介護保険の適用対象となる歩行器は、基本的に「歩行を補助し、安全に移動を支援するもの」に限られます。

介護用品とは?
介護用品とは、介護を必要とする方や介護者が日常生活を支援するために使用する消耗品や道具のことを指します。
福祉用具が長期間使用する設備や機器であるのに対し、介護用品は日常的に使う消耗品や簡単なサポートグッズが中心です。
介護用品の主な種類と特徴
介護用品は、日常生活を快適にするために使われる消耗品や便利グッズが中心です。用途ごとに分類し、それぞれの特徴について解説します。
1. 排泄ケア用品
排泄の負担を軽減し、清潔な状態を保つための用品です。
- 紙おむつ・リハビリパンツ:寝たきりの方や歩行が不安定な方の排泄をサポート。
- 尿とりパッド:紙おむつと併用することで吸収力を高め、漏れを防ぐ。
- ポータブルトイレ用消臭剤:ニオイ対策として必須。消臭・除菌効果があるものも。
2. 清拭・衛生用品
入浴など保清が難しい方の清潔を維持し、感染予防にも役立ちます。
- 介護用ウェットティッシュ:肌に優しい成分で作られており、全身の清拭に適している。
- 口腔ケア用品:歯磨きが困難な方のためのスポンジブラシや口腔ジェルなど。
- 使い捨て手袋:介護の際に衛生を保つために使用。食事介助や排泄ケアにも。
3. 食事関連用品
食事をスムーズに行えるようにするための用品です。
- 介護用スプーン・フォーク:握力が弱い方でも使いやすい、持ち手が太く滑りにくい設計。
- こぼれにくい食器:飲み口が斜めになっているコップや、滑り止め付きのお皿。
- とろみ調整剤:嚥下障害(飲み込む力が弱い方)のために、水分や食事にとろみをつける。
4. 生活サポート用品
介護を受ける方の安全を守り、QOL(生活の質)を向上させるための用品。
- 介護用シューズ:転倒防止のため、滑りにくく、脱ぎ履きもしやすい設計。
- 転倒防止マット:ベッドや椅子からの転落・転倒時の衝撃を和らげる。
- 介護エプロン:食事の際の衣服汚れを防ぐ。防水仕様のものもあり、洗濯が簡単。
介護保険と介護用品
介護用品の多くは消耗品であるため、基本的に介護保険の適用外となります。ただし、一部の自治体では、紙おむつなどの費用を補助する制度を設けている場合があります。また100円均一でも介護用品は販売されています。別の記事で100円均一で買える介護用品を紹介します。
YouTube でも100円均一の商品を紹介していますので、よろしければ併せてご試聴ください!
▶︎YouTube動画を見る
ダイソーで見つけたマジで高齢者におすすめ‼︎アイテム5選】
▶︎YouTube動画を見る
【看護師がおすすめ】介護に役立つDAISO商品5選!+1つ
福祉用具と介護用品の違いまとめ
| 項目 | 福祉用具 | 介護用品 |
|---|---|---|
| 目的 | 自立支援・介護負担の軽減 | 介護を補助し、生活を快適にする |
| 例 | 車椅子、介護ベッド、歩行器 | 紙おむつ、介護用スプーン、消臭剤 |
| 介護保険の適用 | 一部適用(レンタル・購入補助あり) | 基本的に適用外 |
| 使用期間 | 長期間 | 短期間(消耗品が多い) |

福祉用具と介護用品の選び方
1. 利用者の状態を考慮する
- 歩行が不安定な方 → 歩行器や杖など
- 排泄が困難な方 → ポータブルトイレなど
- 寝たきりの方 → 褥瘡予防マットレスや介護用ベッドなど
2. 介護保険の適用を確認する
福祉用具は介護保険の適用があるため、要介護認定を受けられている方は、まずはケアマネージャーに相談しましょう。また、要介護認定を生けられていない方も、まずは介護認定を受けることができるかなど、市区町村にある地域包括支援センター、または役所の高齢者福祉窓口に相談してみてください。
3. 使いやすさや環境に合わせる
福祉用具や介護用品を選ぶ際は、利用者の生活環境や身体状況に適したものを選ぶことが重要です。以下のポイントを考慮すると、より快適に使用できます。
① 家の広さに合わせたサイズを選ぶ
使用するスペースが十分に確保できるかを確認しましょう。
例えば:
- 車椅子や歩行器は廊下やドアの幅を考慮し、スムーズに移動できるサイズを選ぶ。
- 介護ベッドは設置スペースを確保し、介助者が十分に動ける余裕があるかをチェック。場合によっては模様替えも考える、
- ポータブルトイレは、寝室やリビングの配置に合わせてコンパクトなものを選ぶと便利。もちろん体格の考慮も必要。
② 使う人が負担なく使えるものを選ぶ
ご利用者様の身体能力や介護者の負担を考慮した選択が必要です。
例えば:
- 握力が弱い方 → 軽量で握りやすい介護用スプーン・フォークを選ぶ。
- 体を起こすのが難しい方 → 電動リクライニング機能付きの介護ベッドを活用。
- 力を入れて歩くのが難しい方 → 軽量タイプの歩行器を選ぶ。
③ 使い勝手や手入れのしやすさを考慮する
介護用品は日常的に使用するため、手入れのしやすさも重要です。
例えば:
- 防水・撥水加工のある介護エプロンやマットなら、お手入れが簡単。
- 取り外し可能なクッション付きのシャワーチェアは、清潔に保ちやすい。
- キャスター付きのポータブルトイレは、移動や掃除がしやすく便利。
まとめ
福祉用具と介護用品は、どちらも介護を支えるために重要な役割を果たしますが、福祉用具は長期間使用し自立支援に役立つもの、介護用品は日常的に使う消耗品が中心という違いがあります。それぞれの特性を理解し、適切に活用することで、利用者の生活の質を向上させるとともに、介護者の負担も軽減できます。
特に福祉用具は、ご利用者様の身体機能の維持・向上に役立つものが多く、適切な選択によって、より快適で安心な生活を送ることができます。一方で、介護用品は日々の介護をスムーズにするための重要なアイテムであり、継続的な補充が必要なものも多いため、費用や供給方法も考慮しながら選ぶことが大切です。
また、介護保険を利用できる福祉用具については、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談しながら、ご利用者様の状態や生活環境に適した最適なものを選ぶことが重要です。適切な用具を選ぶことで、自立した生活を促し、介護者の負担を軽減することにもつながります。
介護をする上で、福祉用具と介護用品をうまく活用し、より良い介護環境を整えていきましょう。

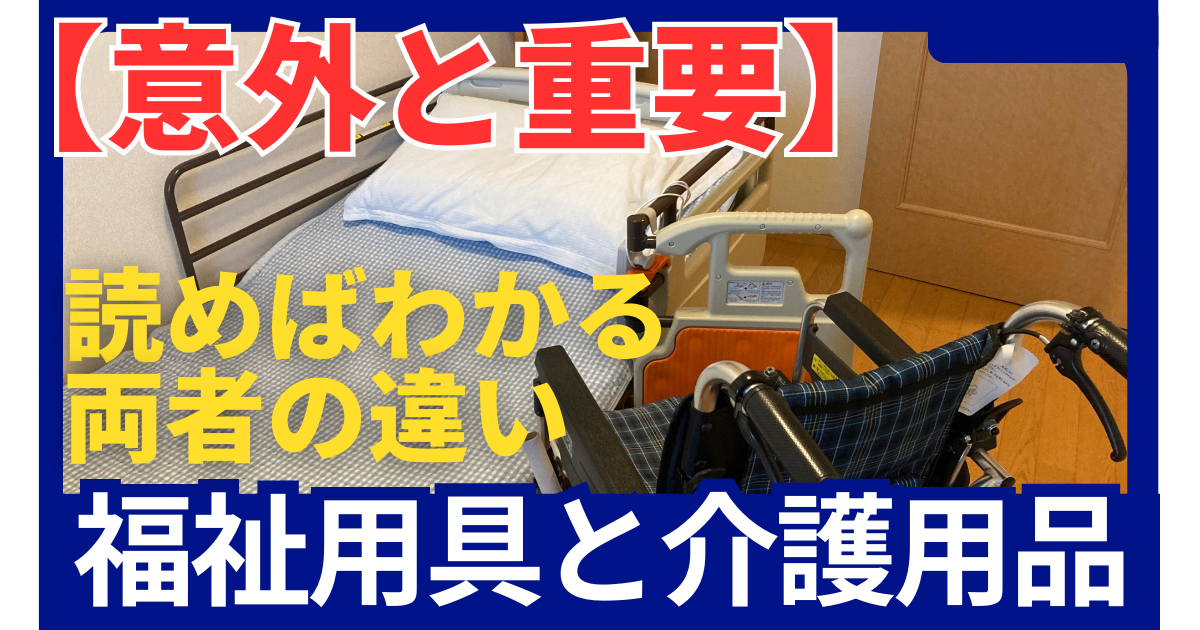

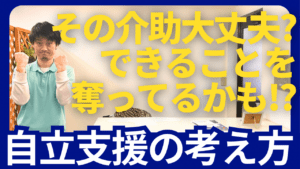
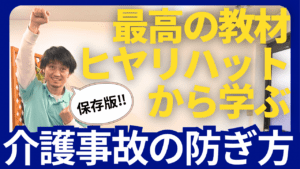
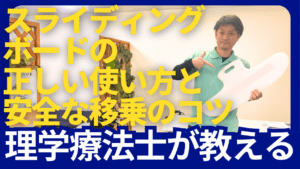
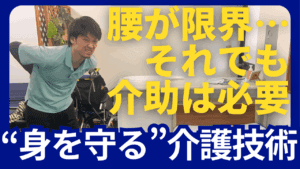
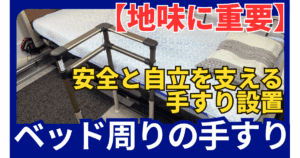

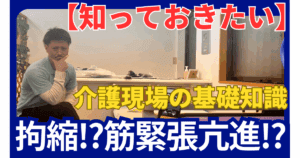
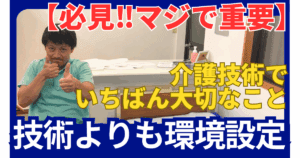
コメント