はじめに
福祉用具は、介護が必要な方やその家族、介護者の負担を軽減し、QOL(生活の質)を向上させるために欠かせないものです。しかし、車椅子や介護用ベッドなど見慣れたものでも正しい使い方はわからなかったり、普段見慣れないものだと尚更で、「どんな福祉用具があるの?」「どうやって選べばいいの?」「実際に使うときのポイントは?」と悩む方も多いと思います。
福祉用具は、正しく選び、適切に活用することで、介護の効率を上げるだけでなく、ご利用者様の自立を促し、自立支援につながる補助が可能になり、快適な生活をサポートすることができます。しかし種類が多く、それぞれの特性や使い方を知らないと、せっかく導入しても十分に活用できないケースもあります。
本記事では、福祉用具の基本から種類、選び方、活用方法までを詳しく解説します。初心者の方でも理解しやすいようにわかりやすくまとめているので、「これから福祉用具を使いたい」「どんな種類があるか知りたい」と考えている方は、ぜひ最後までご覧ください!
福祉用具とは?(基礎知識)
福祉用具とは、高齢者や障がい者が日常生活を安全かつ快適に過ごし、自立した生活を送るために使用する器具や機器のことを指します。これには、移動や食事、排泄、入浴、介護の負担軽減など、さまざまな生活シーンを支えるための道具が含まれます。
たとえば、歩行をサポートする杖や歩行器、ベッドからの立ち上がりを補助する手すり、入浴時の安全を確保するバスボードやシャワーチェア、褥瘡(床ずれ)予防のマットレスやエアマット、背上げ機能や高さを変えられる機能のついた特殊寝台(介護用ベッド)などが代表的な福祉用具です。また、介護する側の負担を軽減するための介護リフトや介護ベルト、排泄を補助するポータブルトイレなども福祉用具に含まれます。
福祉用具は、使用する方の身体状況や生活環境に応じて選ぶことが重要であり、適切に活用することで、より快適で安全な日常生活を実現させることができます。
福祉用具の役割
福祉用具は、介護が必要な方の生活をサポートするだけでなく、介護者の負担を軽減する役割も担っています。使用することで、安全性が向上し、自立した生活を続けるための大きな助けとなります。ここでは、具体的な役割と代表的な福祉用具について詳しく解説します。
移動をサポートする福祉用具
移動が困難な方にとって、安全かつスムーズに移動できることは生活の質を向上させる重要な要素です。移動支援のための福祉用具には、以下のようなものがあります。
- 車椅子:屋内・屋外での移動を補助する一般的な福祉用具。電動車椅子や自走用車椅子、介助用車椅子など、用途に応じた種類がある。
- 歩行器:歩行が不安定な方のバランスをサポートし転倒防止につなげたり、体力が衰えてる方が使うことにより、体力面のサポートとなり行動範囲が広がる。室内用・屋外用、車輪がついているもの・ついていないものなどさまざまなタイプがある。
- 杖(T字杖・ロフストランドクラッチ・四点杖、松葉杖など):歩行時の支えとなり、転倒を防止する。利用者の体力や歩行能力に応じた選択が必要。
- スロープ:段差や階段の昇降をサポートし、車椅子の移動をスムーズにする。玄関や屋外の段差解消に役立つ。

排泄や入浴を補助する福祉用具
排泄や入浴の動作は、介護が必要な方にとって大きな負担となることがあります。福祉用具を活用することで、ご利用者様の自立支援や介護負担の軽減が可能になります。
- ポータブルトイレ:ベッドのそばに設置できるため、夜間や移動が困難な方の排泄をサポート。洗浄機能付きや脱臭機能付きなど、多機能なものもある。消臭剤など様々なトイレ周りのグッズもあり。
- シャワーチェア:浴室内で座ったまま体を洗える椅子。高さ調整や背もたれ付き、ひじ掛け付きのものなど、利用者の状態に合わせた種類がある。
- 浴槽台(バスボード):浴槽への出入りを補助し、転倒リスクを軽減する。浴槽のふちに設置するタイプや、座面がスライドするタイプなどがある。
- 入浴用リフト:入浴時の移乗をサポートする機器。介護者の負担を大幅に軽減することができる。

介護者の負担を軽減する福祉用具
介護者が安全に介助を行い、身体的負担を軽減するための福祉用具も多くあります。特に移乗や姿勢変換の際に役立つものが多いです。
- 特殊寝台(介護用ベッド):電動で高さや背もたれの角度を調整できるため、利用者の姿勢変換や起き上がりをサポートし、介護者の負担を軽減。
- 移乗補助具(スライディングボード・マスターベルトなど):ベッドや車椅子への移乗をスムーズにする。腰への負担を軽減し、移乗時の安全性を高める。
- 介護リフト(床走行型・天井走行型):体を持ち上げる際の負担を軽減し、安全に移動をサポート。施設だけでなく、在宅介護でも導入が進んでいる。
- 腰痛ベルト(腰部骨盤ベルト):移乗など力が必要な介助を行う際の腰の負担を分散し、腰痛予防につながる。
ご利用者様の身体を保護する福祉用具
長時間同じ姿勢を続けることで起こる身体への負担を軽減するための福祉用具も重要です。特に褥瘡(床ずれ)や転倒の予防に役立つものが多くあります。
- 褥瘡(床ずれ)予防マットレス:体圧を分散し、長時間の寝たきり状態でも皮膚や筋肉にかかる負担を軽減する。エアマットや高反発マットレスなど、種類が豊富。
- 体位変換クッション:寝返りが困難な方の姿勢変換を補助し、褥瘡を防ぐ。ポジショニング用のクッションなどがある。
- 転倒予防グッズ(床ずれ防止パッド・滑り止めマットなど):ベッドや車椅子からの転落を防ぎ、安全に生活できる環境を整える。センサー付きマットなどもある。
介護保険で利用できる福祉用具について
介護保険制度を利用すれば、一定の条件を満たした福祉用具のレンタルや購入費の補助を受けることができます。これにより、高額になりがちな福祉用具を経済的な負担を抑えて導入できるため、介護を受ける方や介護者にとって大きなメリットがあります。
ただし、介護度(要支援・要介護の段階)によって利用できる福祉用具の種類や適用範囲が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。具体的には、福祉用具のレンタルと購入のどちらが適用されるのか、またどの福祉用具が介護保険の対象になるのかを理解しておくか、担当のケアマネージャーに相談してみましょう。
介護保険でレンタルできる福祉用具(福祉用具貸与)
介護保険では、必要な福祉用具をレンタル(貸与)することが可能です。レンタル対象となるのは、比較的高価でありながら、一時的な利用が想定されるものや、利用者の状態に合わせて調整が必要なものです。
レンタル対象となる福祉用具
(※要支援1・2の方は、一部の福祉用具のみ対象)
- 車椅子(標準型・電動車椅子など)
- 車椅子付属品(クッション、ブレーキ補助具 など)
- 特殊寝台(介護用ベッド)(背上げ・高さ調整機能付き)
- 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール など)
- 床ずれ予防用具(エアマットレス など)
- 体位変換器(寝返りを補助するクッション など)
- 認知症老人徘徊感知機器(センサー付きの見守り機器)
- 移動用リフト(吊り具付き)(天井走行型や据え置き型など)
- 手すり(設置型のもの)
- スロープ(車椅子で段差を越えるためのもの)
- 歩行器(四輪歩行器、交互歩行器 など)
- 歩行補助杖(多点杖 など)
これらのレンタルは、要介護認定を受けている方であれば、原則1割~3割の自己負担で利用できます(所得に応じて負担割合が変わります)。
また、福祉用具は利用者の状態に合わせて適宜交換できるため、状況が変化しても最適な用具を選べるというメリットがあります。

介護保険で購入できる福祉用具(特定福祉用具販売)
介護保険では、レンタルが難しい福祉用具について、購入費用の補助を受けることができます。ただし、購入できるのは厚生労働大臣が定めた特定福祉用具のみで、年間の上限額(10万円)の範囲内で、自己負担1割~3割で購入可能です。
購入対象となる福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座 など)
- 入浴補助用具(シャワーチェア、浴槽台、浴室内すべり止めマット など)
- 簡易浴槽(空気で膨らませるタイプの浴槽 など)
- 移動用リフトのつり具の部分(リフト本体はレンタル対象)
- 自動排泄処理装置の一部(尿や便を自動で吸引する装置の特定部分)
この制度を利用すれば、高額になりがちな介護用品を比較的安価に購入できるため、在宅介護を行う家庭にとって大きな支援となります。
なお、購入費の補助を受けるためには、事前にケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談し、適切な申請手続きを行う必要があります。
レンタル・購入のまとめ
介護保険を活用することで、福祉用具のレンタルや購入費の補助を受けることができます。
- レンタル対象:車椅子・介護ベッド・歩行器・手すり・スロープなど
- 購入対象:ポータブルトイレ・シャワーチェア・簡易浴槽など
福祉用具を適切に活用し、ご利用者様と介護者の負担を軽減しましょう!
福祉用具の選び方のポイント
福祉用具を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- 使用する方の状態に合ったものを選ぶ(身体能力や認知機能に応じて選択)
リハビリ職が介入している場合は専門職に、もしくは福祉用具専門相談員に選定してもらう。 - レンタルと購入の違いを理解する(介護保険適用でレンタルできるものも多い)
先走って購入してしまうと損してしまうこともあります。 - 実際に試してから決める(展示場やデモ機の活用)
福祉用具の事業所の場合は、購入品でもデモ機がある場合があります。
各福祉用具の選定の詳しい説明はそれぞれ別記事にしていきますので、そちらの記事も併せて読んでみてください。
介護用品との違い
「介護用品」と「福祉用具」は似たような意味で使われることが多いのですが、厳密には異なります。
介護用品とは?
介護用品とは、介護を必要とする方の生活を支えるための一般的な道具や消耗品を指します。特に、日常的に使用するものや衛生管理に関する商品が多く含まれます。
例:
- 紙おむつ・尿とりパッド
- 介護用食器(持ちやすいスプーン・軽量コップなど)
- 食事補助用品(とろみ剤、嚥下補助食品など)
- 防水シーツ・介護用エプロン
- 口腔ケア用品(スポンジブラシ、口腔保湿ジェルなど)
- スキンケア用品(保湿クリーム、清拭用シートなど)
- 介護用衣類(介護パジャマ、着脱しやすい衣類など)
特徴
- 主に消耗品や小型の道具が中心
- 介護する人・される人の負担を減らすためのもの
- 介護保険の適用外が多い(基本的に自己負担で購入)
介護用品と福祉用具の違いまとめ
| 項目 | 介護用品 | 福祉用具 |
|---|---|---|
| 目的 | 介護の補助、衛生管理 | 生活の質の向上、自立支援 |
| 対象 | 介護する人・される人の負担軽減 | 主に介護される人の自立を助ける |
| 種類 | 消耗品や小型の道具が多い | 移動・排泄・入浴を補助する道具が多い |
| 介護保険適用 | 原則適用外(自己負担) | 適用されるものが多い(レンタル・購入補助あり) |
| 具体例 | 紙おむつ、食器、スキンケア用品 | 車椅子、介護ベッド、手すり、歩行器 |
簡単に言うと…
- 「介護用品」は「日常的に使う消耗品や便利グッズ」
- 「福祉用具」は「自立支援や身体補助のための機器や器具」
この違いを理解することで、必要なものを適切に選び、より快適な介護環境を整えることができます。
※介護用品を詳しく解説した記事はまた別にまとめていますので、そちらの記事も読んでみてください。
まとめ
福祉用具は、介護の負担を軽減し、ご利用者様が安全で快適に生活できるようサポートする重要なアイテムです。
用具の種類を理解し、適切なものを選ぶ
移動・入浴・排泄・介護負担軽減など、用途に合った福祉用具を選びましょう。
介護保険制度を活用し、費用負担を抑える
介護ベッドや車椅子などは、介護保険を利用してレンタルや購入補助を受けることが可能です。
正しい使い方をマスターして、介護をスムーズにする
安全かつ効果的に使うために、正しい使用方法を学び、必要に応じて専門家のアドバイスを受けましょう。
このブログでも随時更新していきます。
福祉用具を上手に活用し、より快適で安心できる介護環境を整えましょう!
YouTubeでも様々な福祉用具を紹介し、使い方も詳しく解説しておりますので、再生リストも用意しております。
お時間を許す時に見てみてください。
▶︎福祉用具のいろいろ
https://www.youtube.com/watch?v=xRcJa6qXyLU&list=PLMGm4_HP1IHrbgfvrKDxsh4IFwKZFQZlh

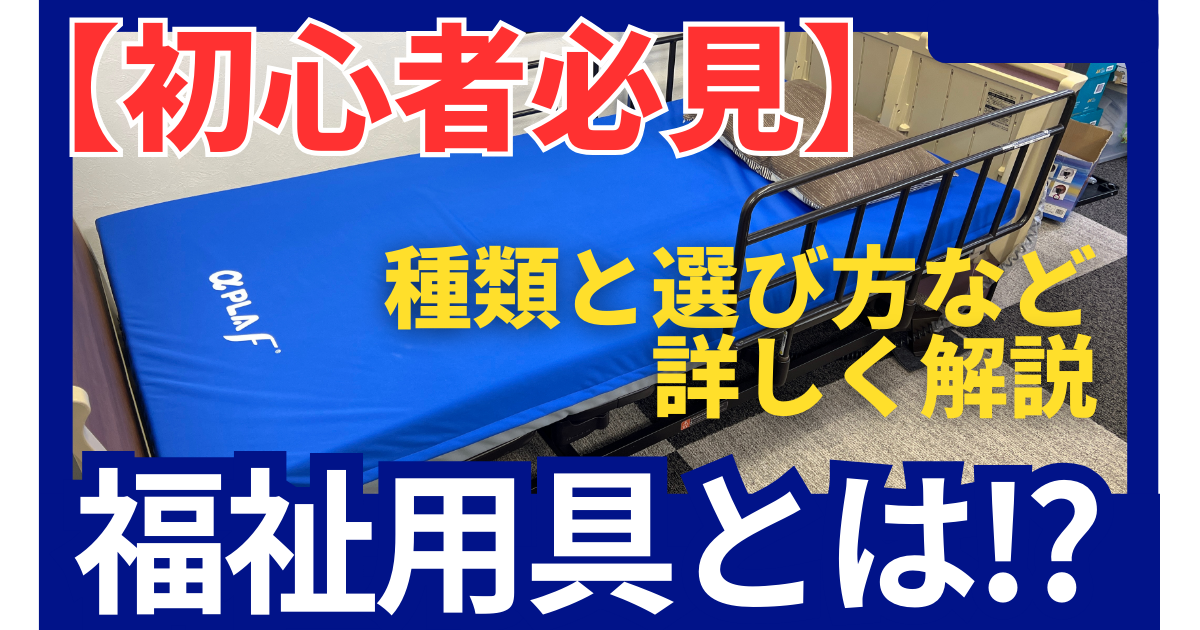

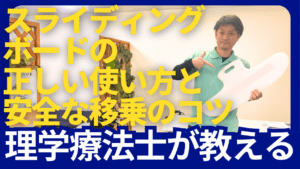
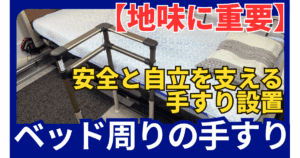

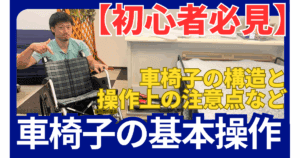
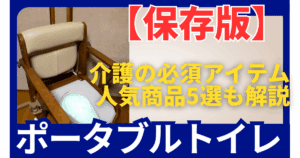
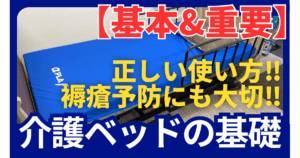
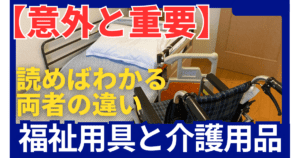

コメント