はじめに
ベッドからの起き上がりや立ち上がり、車いすやポータブルトイレへの移乗など――
私たちは一日の中で、無意識のうちに何度も「立つ・座る・移る」といった動作を繰り返しています。
しかしこれらの動作は、転倒事故が最も多く起こる場面のひとつです。
特に高齢者の場合は、
- 下肢筋力の低下
- バランス感覚や反応速度の衰え
- 視力・判断力の低下(特に夜間)
- 薬の副作用によるふらつき
など、さまざまな要因が重なり、わずかなきっかけで転倒してしまうことがあります。
転倒によって骨折や頭部外傷を負うと、そのまま寝たきりや入院生活に移行してしまうリスクもあり、生活の自立を大きく損なう原因になります。
こうした事故を防ぎ、安心して起き上がり・立ち上がり・移乗動作を行うために有効なのが、「ベッド周りへの手すりの設置」です。
手すりは、単に「転ばないための道具」ではありません。
適切に設置することで、
- ご利用者様の自立動作を促し
- 介助者の身体的負担を軽減し
- 日常生活の安全と安心を守る
大切なサポートツールです。
ベッド周りの手すりを設置する3つの目的
① 転倒を防ぐ
ベッド周辺は、立ち上がりや座り動作、移乗などの「転倒リスクが高い動作」が集中する場所です。
特に起床直後や夜間のトイレ移動時は、体がまだ覚醒しておらず、ふらつきや立ちくらみが起こりやすくなります。
そのようなとき、手すりをしっかり握って身体を支えることで、
- バランスを崩した際の転倒防止
- 起き上がる際の安定した支点の確保
- 夜間でも安全に移動できる環境づくり
が実現できます。
また、手すりの高さや位置を正しく調整することで、体の重心移動がスムーズになり、膝や腰への負担も軽減します。
つまり手すりは、転倒予防だけでなく、身体にやさしい動作を促すリスクマネジメントツールでもあるのです。
② 自立動作を支える
手すりの本来の目的は、ただ支えることではなく、「自分で動けるようにすること」です。
起き上がり・立ち上がりの際に手すりを利用することで、「自分の力でできた」という小さな成功体験が積み重なります。
この体験が、
- 「もう少し歩いてみよう」
- 「次は介助なしでやってみよう」
という自立への意欲を高め、リハビリ効果の向上にも直結します。
さらに、自分でできる動作が増えると、介助を受けることへの抵抗感が減り、精神的な自立にもつながります。
リハビリ現場では、この「自分で動ける」という意識の変化こそが、機能回復の大きな第一歩です。
③ 介助者の負担を軽減
手すりの設置は、ご利用者様のためだけではありません。
介助を行う家族や介護職員にとっても、身体的・心理的な負担を軽くする効果があります。
例えば、
- 立ち上がりの際に支える量が減る
- ベッド移乗時の介助姿勢が安定する
- 転倒リスクへの不安が軽減する
といったメリットがあります。
ご利用者様が手すりを活用して自立的に動ける範囲が広がれば、その分介助の回数も減り、介助者の腰痛や疲労の予防にもつながります。
ベッド周りの手すりの種類
1. ベッド本体取り付けタイプ
ベッドのフレームに差し込み、固定して使うタイプ。
最もポピュラーで、設置も容易です。
特徴:
- 起き上がり・立ち上がり時の支えに最適
- 高さや角度を調整できる製品も多い
- ベッドの形状との適合を確認する必要あり

2. 自立式(床置き)タイプ
ベッドの横に独立して置くタイプで、設置場所を自由に選べるのが特徴で、型も様々なので、その方に合ったものを選択することができます。
特徴:
- 壁やベッドに固定しないため移動可能
- リハビリや動線調整にも対応
- 床が滑らない場所に設置することが重要

ベッド周りの手すりが活躍する場面
① 起き上がり動作の補助
ベッドの側面に手すりを設置することで、寝返りから上体を起こす一連の動作をスムーズに行うことができます。
とくに体幹や腕の力が弱くなっている方にとっては、「つかまる場所がある」だけで動作の安定感が大きく変わります。
手すりは、寝返り→上体起こし→座位保持という自然な流れの中で、無理なく手が届く位置にあることが大切です。
肘が軽く曲がる程度の高さが理想で、床置き型のベッドサイド手すりなら微調整も可能です。
また、手すりがあることで、夜間や起床時にも安心して動くことができます。
起き上がる時のポイントとしては、ベッドから先に足を出すことを意識してみてください。
② 立ち上がり動作の補助
ベッドの側面に縦型(L字型)の手すりを配置することで、立ち上がり時のふらつきを防ぎます。
また、上体を前に傾けやすくなり、足に体重をかける「重心移動」がしやすくなります。
手すりの高さは杖や歩行器と同じく、大転子の高さに設定します。
歩行器の高さ設定はこちらの記事で詳しく書いていますので、こちらも見てみてください。
▶︎【プロが教える】歩行器の正しい高さ設定【重要】
手すりを軽く握って腕で支えることで、脚だけに頼らない安全な立ち上がりが可能になります。
また、立ち上がるたびに介助を要していた方でも、手すりを使うことで自立的に行えるようになるケースも多く見られます。
立ち上がる際は「お辞儀」を意識してもらい、前方への重心移動を促してあげてください。
③ ベッドからの移乗動作の補助
ベッドから車いす、ポータブルトイレ、歩行器などへ移乗する際にも、手すりは欠かせません。
手すりを利用することで動作の流れが自然になり、介助者の負担も軽減します。
とくに、立ち上がってから方向転換をする際や、座る瞬間にバランスを崩しやすい方にとっては、最後までつかまれる支点があることで転倒リスクを大幅に減らすことができます。
手すりの位置としては、②と同様に側面に縦型(L字型)の手すりを配置し、高さは大転子の高さに設定します。
手すりを設置するときの注意点
ベッド高さとのバランスを確認
手すりの効果を最大限に発揮するためには、まずベッドの高さとのバランスが重要です。
ベッドが高すぎると足が床につかず、立ち上がる際に体が前に倒れやすくなります。逆に低すぎると、膝や腰への負担が大きくなり、スムーズに立ち上がれません。
一般的には、座面高40cm前後がひとつの目安とされていますが、座った時に太ももがやや斜め下を向く角度(水平より少し膝が下がる程度)が理想的です。この姿勢は、体重を前方に移動しやすく、下肢の力をしっかり使って立ち上がることができます。
また、足裏全体がしっかり床につくことも大切です。足が浮いていたり、つま先だけしか接地していない状態では、踏ん張りがきかず、立ち上がりやすさだけでなく、転倒リスクも高まります。
ご利用者様の身長や使用しているベッドの種類に合わせて、ベッドの高さを微調整することがポイントです。

夜間照明を併用する
夜間、トイレへの移動や寝返り・起き上がりを行う際には、照明の工夫も欠かせません。
暗闇の中で手すりを探す動作は危険を伴います。特に高齢者の場合、暗さによる視覚の低下やふらつきが転倒につながることもあります。
手すりの近くに足元灯や人感センサー付きライトを設置しておくと、立ち上がる動作に合わせて自動で点灯し、安心です。
また、眩しすぎる照明はかえって目がくらむ原因になるため、やわらかい光のLEDライトを選ぶと良いでしょう。
設置場所を定期的に点検
手すりは、一度設置して終わりではありません。日常的な使用によって、ネジの緩みや設置面のガタつきが生じることがあります。
緩んだ手すりは、逆に転倒の原因になりかねません。特に、床据え置きタイプの自立型手すりは、位置が動いていたりすることもありますので、定期的に点検・再固定を行うことが大切です。
もしご利用者様が「最近、手すりが動く気がする」「少し不安定」と感じている場合は、早めに福祉用具専門相談員やケアマネージャーに相談しましょう。
安全に長く使うためには、月に1度程度の簡単なチェックを習慣にするのがおすすめです。
介助者の動線も考慮
手すりはご利用者様のために設置するものですが、介助者の動線を妨げないことも忘れてはいけません。
たとえば、ベッドサイドにL字型の手すりを設置すると、立ち上がりは楽になりますが、そのすぐ横で介助者がサポートする際にスペースが狭くなる場合があります。
介助動作の多い場面では、あらかじめ実際に介助の姿勢を取ってみて、十分な動きのスペースが確保できるかを確認しておくことが重要です。特に介助量が多い場合は、手すりがかえって邪魔になる場合もあります。そういったケースでは角度を変えることができる介助バーが最適だと考えられます。
介助バーだと、座位保持の際には、直角に設定した手すりを握っていただき、移乗の際は介助に邪魔にならない角度に設定することができます。
手すりの設置は、「付ければ安心」というものではなく、高さ・位置・環境とのバランスが何よりも大切です。
ご利用者様が安全に、そして自然な動作で立ち上がれるようにするためには、環境全体を見直す視点が欠かせません。
介助者と一緒に試しながら、最も使いやすい位置を見つけていくことが、事故防止と自立支援の両立につながります。
まとめ
手すりは「安心と自立」をつなぐパートナーです。
ベッド周りの手すりは、単なる転倒防止具ではなく、
「自分の力で生活するための支え」です。
適切な位置・高さ・種類を選ぶことで、
- ご利用者様の自立を促進し、
- 介助者の身体的負担を軽減し、
- 安全で快適な生活空間をつくることができます。
毎日の起き上がりや立ち上がり、移乗を安心して行える環境づくりは、リハビリ・介護の第一歩といえると思います。
あわせて読みたい記事
▶︎【プロが教える】歩行器の正しい高さ設定【重要】
▶︎特殊寝台(介護用ベッド)の正しい使い方と選び方
▶︎介護技術で一番大事なこと、それは“環境設定”だった
YouTubeでも環境設定の大切さを解説しています。合わせてご視聴してみてください。
▶︎【環境設定が1番大事】介護の負担や事故を減らすために大切なこと




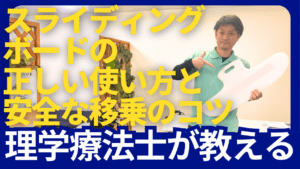

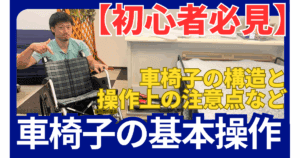
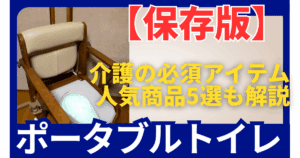
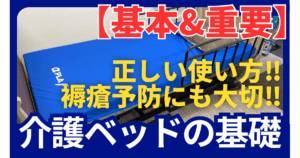
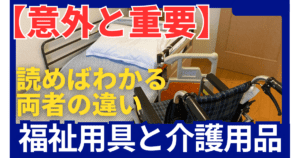

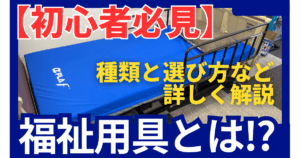
コメント